前口上
例えばこのような物語がある。勝者総取りのゼロサムゲームを企画し、弁舌巧みに登場人物たちを参加させるゲームマスターが存在する。主人公もしくはその対となる人物はルールブレイカー、少なくともルールの穴を追い求める者として設定される。
また、参加者たちはよく見知った、それでいて単なる友人ともいえない少女たちである。
加えて、何らかの理由により時間をループさせる者が登場する。
そして、キリンが存在する。
これは「舞台少女」を名乗る者たちによる「少女歌劇」と銘打たれた、奇妙な歌劇。もしくは……
舞台少女は演技をしない(?)
『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』のポジション・ゼロは掴みづらい。
聖翔音楽学園に通う8人の「舞台少女」たちと、転校生の神楽ひかりを加えた9人は、夜な夜な謎のキリンから呼び出しを受け、「オーディション」というレヴューに参加している。合格者には「トップスターの座」が与えられ、合格者の望んだ「運命の舞台」が誂えられる。
「オーディション」開催時、彼女たちは各々の衣裳に着替えるのだが、それは変身ではない。日常世界と「オーディション」の世界での振る舞いはほとんど連続性を保っていると言っていいし、むしろ彼女たちは「オーディション」の場において日常世界よりもはっきりとした物言いを相手にぶつけていく傾向がある。歌い、剣を手に舞い、トップスターの座を奪いあうとしても、あまりに日常世界から切断されていない台詞が演技から演技を奪っていく。ここでは武芸の熟練度ではなく、相手よりも強く、真実に迫った思いを持っているのかどうかが結局のところ勝負を分けているように見える。スター性が基準であるなら天堂真矢は大場ななに負けないだろうから(ところで強い思いや真実味というのは何であり、一体どういった理由で尊重されているのだろうか?)。ここにあるのは武装した少女たちの演技というよりも、少女たちが武装した日常である(言うまでもなく、舞台少女たちに限らずA組の生徒たちにとってオーディションは「オーディション」だけではない)。
では、「オーディション」の世界の方が素顔であり、日常世界でこそ少女たちは演技をしているのだというべきなのだろうか。それも腑に落ちない。なぜなら各「オーディション」終了後、舞台少女たちは「オーディション」で起こったことを前提にして会話をし、相互理解を深めていくからだ。私たちは普段嘘をついたり、あえて何かを言わずにおいたり、ごまかしたりすることがある。しかし日常にそういった部分があることをもって、私たちは日常世界で演技をしているとは言わない。
私たちは舞台少女の演技を、練習風景や、9話における第99回聖翔祭公演『スタァライト』の回想を用いた愛城華恋とひかりの会話の中で確認することができるだけにとどまる。劇場版では露崎まひるがひかりに対して作中最も長い「演技」を見せるかに思われるが、これとて日常的に我々が用いる「演技」であって、舞台の上としての演技というわけではなかろう。舞台少女の構成要素である演技が、滑り抜けていく。
少女たちだけではない。劇中最も謎めいたフレーズである「アタシ再生産」もまた、その意味を掴ませることを拒み続ける。
華恋の着替えのシーンに登場する、衣裳の縫製に似合わない熔鉄。これは作品世界全体のモチーフであろう宝塚歌劇の創設者・小林一三が、日本の工業化黎明期において最も(文字通り)資本を多量に消費したであろう私営鉄道の経営者であったことを即座に思い起こさせる。「ゲーム」は熾烈な競争と巨大なリスクを舞台少女に強いているし、「アタシ再生産」という言葉はこれらの要素との繋がりの下に明らかになるのだろうという予測がつくが、事態はそう簡単にはいかない。
愛城華恋は確かに舞台少女たちの中で、日常世界と「オーディション」での振る舞いが一番なめらかに繋がっている人物ではある。では「アタシ再生産」とは、変身してもアタシはアタシでありつづけるという強みを謳いあげるフレーズなのであろうか。そうはならない。日常世界と「オーディション」での振る舞いの差はどの舞台少女にしても微々たるものであり、別に華恋だけが特別ではない。
極めて類型的に形成されている舞台少女たちを掘り下げる回でのドラマはほとんど予想の域を超えず(私にとって例外だったのは花柳香子で、私は香子が石動双葉の知らないところで特訓を怠っていないものだと思っていたが、正解はそうではない方だった)、煌びやかな音楽と舞台装置の力でなんとか物語は進んでいく。中盤を経て大場ななが、スターになることを諦めた者や、演劇の楽しさを教えてくれた仲間たちとの別れによって、大切な人たちが傷つくことを嫌い、最高にキラメいていた過去の公演を繰り返し「再演」していたということが明らかになる。この試みは確かに「ゲーム」へ抵抗しうる要素を含んではいるが、華恋は第9話の「オーディション」で、ななにこう言い放つ。
舞台少女は日々進化中……!同じわたしたちも、同じ舞台もない!どんな舞台も一度きり、その一瞬で燃え尽きるから、愛おしくて、かけがえなくて、価値があるの!一瞬で燃え上がるから、舞台少女はみんな、舞台に立つ度に新しく生まれ変わるの!
「愛」という有史以来最も著名なバズワードを除けば、ここには労働者の自己啓発と、経済学において商品を定義するための三要素すなわち、対象の物理的特性・利用可能な場所・利用可能な時間に則って説明される舞台少女の稀少性、そしてついでに耐久消費財をいかにして経済学理論が取り扱うかという簡潔な比喩、これらが凝縮されている。
こうしてななは華恋に敗北し、星見純那と語らう。
「欲張り過ぎたのかな……」
「え……」
「あの一年がもっと楽しく、もっと仲良くなれるようにって、『再演』の度に少しずつ台詞をいじったり、演出を加えたりした……でも、ひかりちゃんがきて、華恋ちゃんが、変わって、みんなも、どんどん変わって……わたしの『再演』が、否定されていくみたいで怖かった。だけど、新しい日々は刺激的で、新しいみんなも魅力的で……どうしていいのか、分からなくなって……」
「なあんだ、あなたもちゃんと、舞台少女なんじゃない」
ななの欲望が持っていた「ゲーム」への抵抗という側面は、こうして私的な圏域で再解釈されることによって沈降していく。少々悪辣に華恋とななの台詞を読んでみたが、それでは「アタシ再生産」とは華恋の「ゲーム」に対する圧倒的な適合性を示すのだろうか。そうはならない。「オーディション」終了後、舞台少女たちの「罪」を一人で背負い塔に幽閉されたひかりを助けるため、華恋はひかりが口にするところの「運命」を変えるべく、ひかりが自らに与えた「伝説の舞台」に突貫する。無限に繰り返されるひかりの『スタァライト』一人芝居に介入する華恋は、一度ひかりに敗れ、ひかりは幾度となく「再演」されたであろう第99回聖翔祭公演『スタァライト』の最後を締めくくる台詞「ふたりの夢は、叶わないのよ……」を言い切るのだが、華恋は脚本を改変し、復活する。キリンは「『伝説の舞台』の、再生産……!」と感極まり、「フローラ」と「クレール」という呼びかけは、「華恋」と「ひかりちゃん」に変わる。華恋の「革命」はひかりに怖れをもたらす。「そんなことしたら……わたしの『運命の舞台』に囚われて、華恋のキラメキも奪われちゃう!」というひかりに、華恋は答える。
「奪っていいよ!わたしの全部!」
「……!」
「奪われたって終わりじゃない!失くしたってキラメキは消えない!舞台に立つ度に、何度だって燃え上がって生まれ変わる!」
「……東京、タワー……!」
そして発されるのがあの「アタシ再生産」である。「ひかりちゃんをわたしに、全部ちょうだい!」という台詞といい、12話での華恋はもはや競争からの脱落が即絶望(「絶望」とは、ななが自身「再演」し続けていた舞台において演じていた幽閉された女神の罪である)を意味するわけではないこと、キラメキと市場価値は異なることを知っており、キラメキを含めた自分自身全体を贈与し、またひかりが自身に贈与することを求める(私自身は贈与なる概念が「資本主義」に対抗しうる位相にあるかのように語られることに疑念を持っているが)。だがその彼女はその場面においても「アタシ『再生産』」を言う。「オーディション」の主催であると同時に観客の機能を背負うキリンもまた12話の山場で「再生産」を口にしており、その意味はけして肯定的に解消され尽くすものではない。劇場版において「アタシ再生産」が華恋の口から発せられる時、それはただの復活を意味しているように観えてしまう。
華恋は「再生産」を資本主義の文脈(私は「資本主義」も「新自由主義」も気に入らないものを全部投げ込めるゴミ箱になってしまったと感じているため出来る限り使いたくないのだが)とは違った文脈で使えるようになったということなのだろうか?そう言い切れるだけの材料はまったく不足している。
こうして「アタシ再生産」は滑り抜けていく。
東京タワーは何度も華恋とひかりの想い出の場所として現れ、二人でスタァライトするという未来は華恋からひかりに向けては「約束」として、ひかりから華恋に向けては「運命」として東京タワーに結びつけられるが、12話にてひかりの悲しい「運命」を華恋は打ち破ったのだから、東京タワーが倒れるのは理にかなっているが、それでは約束はどうなるのかというと、なんとテロップで「約束タワーブリッジ」と表示される。二人はスタァライトの頂に上り、約束は文字通り果たされ、東京タワーは滑り抜けていく。
この物語には、舞台少女たちの物語とは別の軸がある。それがキリンである。
キリンは観客席で「首を長くして(実際これ以外の比喩が私には今のところ思いついていない)」舞台少女たちのキラメキを待ち望んでいるが、「オーディション」の主催者でもある。「わかります」が口癖のキリンは「完全に理解した」がる画面の向こう側の観客の性向とよく同期しており、そう明示されなくとも自身が観客であることを何度もキリン自身語っている。
それが12話で、キリンは唐突に画面の方を向き、鑑賞者に向けて語りはじめる。
なぜわたしが観ているだけなのか分からない?
わかります。
舞台とは、演じる者と観る者が揃って成り立つもの。演者が立ち、観客が望むかぎり続くのです。
そう、あなたが彼女たちを見守り続けてきたように。
わたしは途切れさせたくない!舞台を愛する観客にして、「運命の舞台」の主催者!
舞台少女たち……永遠の一瞬!迸るキラメキ!わたしはそれが観たいのです!
そう、あなたと一緒に。
実際のところ私が見守ってきたのは舞台少女ではなくてキリンなのだが、それは趣味の問題かもしれない。いずれにせよこの部分はアニメシリーズの中であまりにも唐突に現れるが、端的に言ってキリンによる第四の壁の越境は舞台少女たちの物語となんら繋がっていないように見える。劇場版においてキリンは、新たな舞台の開幕を宣言し、少女たちを新たなレヴューへ誘導し、「舞台」を作るための燃料としての観客という視点を提示して燃え上がりながら落下していく。キリンの存在と舞台少女たちの物語をどう劇場版で噛みあわせるのか、私は期待して映画館に向かったのだが。
とはいえ「わたしは途切れさせたくない」と言いながらキリンが画面のこちら側を真っ正面から見据え、華恋とひかりの戦っている舞台が煙に隠されるカットは素直に興奮した。私はこのまま最後まで、時空を無視し、静止してこちらを向くキリンが画面の右端に映り続けることを願ったが、その期待は叶わず、私たちはあっけなく舞台少女たちの物語を再び曇りなく観ることができるようになる。
(ところで「ワイルドスクリーンバロック」を謳うキリンは時々全身が野菜になったりしていたが、私の拙い知識ではアルチンボルドはマニエリスム、少なくとも後期ルネサンスの画家として認知されており、バロックの画家というイメージはないのだが、どうだのだろうか。)
キリンもまたこうして滑り抜けていった。
舞台少女たちのドラマは規格的であり、演技は脇道であり、キリンは舞台に乗りきることができず、象徴は簡単に象徴であることを止め、アニメを見返す度に華恋だけではなくすべてのキャラクターが、東京タワーが、そして運命の外部へ突き進んだ華恋が再生産される。
これは観客が「わかります」と言うことが禁じられた物語。
……本当に?
舞台少女は演技をする(?)
全12話の中で最も印象に残ったのは4話、外出規則を破って朝帰りを敢行した華恋とひかりを「舞台少女」たちが迎え入れる場面で双葉と香子が喋るシーンだ。
「勝手に家出すんなよ、香子じゃねえんだから」
「ウチ、そんなことしまへん」
二人の部屋のレイアウトから考えると、二人は壁に向かって喋っていることになる。外で純那、なな、まひるがひかりと華恋の前でおかえりを言い、窓ガラス越しに天堂真矢が彼女たちを見下ろしながらおかえりを言う。西條クロディーヌは画面右を向いて「Dienvenue(おかえりなさい)」と呟いているが、これらはアニメとして特に違和感のある画面ではない。だが双葉と香子は壁に向かって、しかも視線が正確にカメラ目線となっている。双葉の後ろで寝ている香子には双葉がどこを向いているかなど分かるはずもないのに。
どうして彼女たちは視点を壁の特定の一点で共有しえたのか。
それは、私たちの観ているものが『テレビアニメ 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』であり、『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』だからだ。
前節で私は舞台少女は演技をしないと示唆したが、それは本当だろうか。舞台にはお芝居があるが、それだけではない。ひかりの言う通り、舞台には踊りも、歌もある。それにどうして彼女たちは「オーディション」に登場する際、聖翔音楽学園(すなわち日常世界)での規則もしくは伝統と同様に出席番号と名前を言うだけでなく口上を述べるのか。ここで私たちはアニメ女優という概念について考えなければならない。
テレビや映画とアニメの違いは幾つもあるが、その一つに演技の位相がある。テレビドラマや映画では、まず演者は正しくこの世界に存在する人間として身体を持ち、その上に演技が重ね合わされることによって日常世界での存在とは別の存在へと変身を果たす(無論CGや着ぐるみの問題はあるが、それはこの基礎の延長線上にある)。だがアニメでは、画面に映る存在とそれを「演じている」存在は存在の位相からテレビや映画の演者と全く異なっている。アニメキャラクターの生成は声優による声の吹き込みと、キャラクターデザイン、作画、編集および撮影……という複数のプロセスを必要とする造形及び運動によってなされる。ラジオドラマでは声だけが、公式サイトのキャラクター紹介欄では絵だけが必要である。このように、アニメはテレビや映画の俳優と異なり、表現されるものと表現するものの一対一対応が壊れている。アニメキャラクターはそれが現れる場の要請に応じて取捨選択する事ができる複数の要素の集合体によって存在しているといえる。
アニメキャラがアニメに現れるとき、彼ら彼女らの構成要素は総動員されるが、アニメキャラが現れる時彼女たちはすでに運命を背負っている。それが脚本である。それはアニメキャラが原理的に突破できない運命である。アニメが複合的な要素からなる集合体であり、ある要素の逸脱があったとしても、それが私たちの目の前に現れる前の段階で逸脱を許容する脚本がアニメを一つの運命としてまとめ上げる。あるいは声優のアドリブとは、脚本がそれを許容しうる範囲に存在するからこそ許されているのだという仕方で同じことが言える。アニメキャラは、表現されるものとしてしか私たちの前に現れることがない。これは私たちがあり得たかもしれないアニメキャラによる革命を見ることが不可能であることを意味しており、「ライブアニメ」が不可能である理由でもある。(ところでVtuberとはいったいどのような存在なのだろうか、あるいはなりうるのだろうか?)。
従ってアニメキャラは演技することができない。このことから容易に「アニメ女優」は不可能であることが帰結する。
……本当に?
あなた方の好きな(もしそうでないならお許し願いたい、私はそのようなあなたと握手がしたい)「想像力」を駆使しなければ、「舞台少女」たちの名前がアニメ女優たちの「役名」であり、私たちは彼女たちの本名あるいは女優名を知らないとは言えないのだろうか。
口上について考えることにしよう。日常生活で私たちは挨拶する時に口上を述べたりしない(今ならヤクザさえしているのか怪しい)。前節のように、舞台少女たちが演技をしないと強弁しようとする時、歌や、踊りとしての戦闘だけでなく、口上の存在がネックになる。口上がなければレヴューへの登場はダンスルームへの入室と同一であり、日常世界と「オーディション」の世界の連続性はより強固なものとなるが、「オーディション」においてのみ口上が存在することは一体なにを意味しているのだろう?
「オーディション」は『スタァライト』の筋書きをなぞるかのようにレヴューのタイトルが決められており、塔に幽閉された女神たちを演じた舞台少女たちは、女神たちの背負った罪をもまた背負っている(純那-激昂、香子=逃避、華恋=傲慢、双葉=呪縛、まひる=嫉妬、なな=絶望)。「オーディション」で舞台少女たちが語る言葉があまりにも日常世界のそれと連続していることは、日常世界の彼女たちがあまりにも『スタァライト』の登場人物たちに似すぎているということを意味しているが、これは偶然というには異様である。
思うに、口上の存在は、4話における双葉と香子の奇妙なカメラ目線と同じ意味を持っているのだ。それは彼女たちが演技をしているという暗号である。この暗号が「オーディション」と「日常世界」の両方から発せられていること、レヴュー名・『スタァライト』の囚われの女神たち・舞台少女たちの抱える思いや状況の異様な符号は、この世界全体が作品であり、彼女たちは画面の中では演技しか見せていないということを示唆するのではないか。『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』が私たちに見せていたのは、文字通り、「トップスターを目指す舞台少女たちの物語」であり、彼女たちは「舞台少女」を演じるアニメ女優たちだったのではないか。
私がこの節を書いている時、「歌って、踊って、奪い合いましょう」と言い、お芝居をオミットしたキリンはエレベーターホールの奥底で眠っている。
そしてスクリーンに舞台少女は現れ……
劇場版において「舞台少女」たちは卒業を控え、それぞれのけじめをつけようとする(おそらく「みんな、喋りすぎ」とひとりごち、電車を舞台に現れた白衣のななが一枚噛んでいるであろう。「舞台少女」であるならば、喋るだけで何とかするというのは不足であり、歌って、踊って、お芝居をするべきだからだ)。ここではなな、クロディーヌ、真矢が演技としか言いようのない振る舞いを見せてくれる。特にクロディーヌ対真矢の対決は圧倒的だった。彼女たちの語る言葉には「脚本」の存在を感じられるが、しかしそれらは日常世界でのけじめをつけるための台詞にもなっていた。この段落は、「舞台少女は演技をしない」ことを否定するのだが、「舞台少女は演技をする」ことの補強にはならない。
私は上映中に周囲を見渡したが、燃え尽きた後のキリンは特にどの席にも座っていなかったように見えたということもできるし、夥しい量のキリンが座っていたということもできる。
劇場版においては華恋とひかりも第四の壁を超えたと解釈できるような台詞を口にするが、少女たちの物語を消費する観客について劇場版が示す態度は、テレビアニメ版のキリンでやろうとしていたこととは別の方向、はっきり言えば軟化していたように思えた。絢爛な背景と音楽は印象的だったが、私はテレビアニメの時点で「舞台少女」たちにはそれほど魅かれていなかったので、画面の速度が緩まる華恋とひかりの回想シーンなどは正直集中力を維持するのが辛かった。
だが期待があった。「私たちはもう舞台の上」という言葉は、舞台少女たちが映っているのがスクリーンであることから彼女たちが女優であることへの可能性を残していた。彼女たちの存在しないスクリーンに「私たちはもう舞台の上」とでも現れれば、彼女たちは私の見えないどこかの舞台の上で、また別の演技をしているのではないか、と思える。もちろん彼女たちは私の拍手に応えることは出来ない。もし画面の中に、演技を終えたように見える彼女たちが現れても映画はそのシーンを含めて映画なのであり、そこは映画の外部ではない。だが……
私はテレビアニメ版のキリンが「あなたと一緒に」と言ってくれたことに感謝している。キリンは簡潔な欲望を素直に口にし、舞台少女たちの見せるキラメキに感動する気持ちの良いキリンだが、このような長ったらしく、嫌味であり、妄想に満ちており、論理もあるのかないのか分からない文章を書いている私は、キリンを欲望し、「生身」のアニメキャラを欲望する気持ちの悪い人間だからだ。
エンドロールを迎え、舞台少女たちは作品世界内に存在する学校や劇団へと散っていった。エンドロールが終わるとそこにはおそらく音楽学校を受験する華恋の姿があった。テロップからして彼女は今まで観客たちが観てきた「愛城華恋」ではないのかもしれない。年齢を考えるとおそらく人生最初の大舞台にいる。そこは体育館か集会場のようであり、椅子があり、長い机の向うに面接官の先生であろう人物がおり、その関係者たちが歩き回っている。確かに舞台然とはしていないが、華恋の「舞台少女」としての歩みは、舞台は、まさに今から始まろうとしていた。
だから私は映画が終わった後、カーテンコールをするのをやめた。
![東京2020オリンピック SIDE:A/SIDE:B [Blu-ray] 東京2020オリンピック SIDE:A/SIDE:B [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61RX7d+x4yL._SL500_.jpg)


![PIANO SOLO [12 inch Analog] PIANO SOLO [12 inch Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/415VFUVtOQL._SL500_.jpg)





![Quality Over Opinion [輸入アナログ盤 / DLコード / ブラックヴァイナル仕様 / 2LP] (BF129)_1628 [Analog] Quality Over Opinion [輸入アナログ盤 / DLコード / ブラックヴァイナル仕様 / 2LP] (BF129)_1628 [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/31xCs+ZdQUL._SL500_.jpg)
![Blind [輸入アナログ盤 / DLコード / 1LP] (BF111)_1506 [Analog] Blind [輸入アナログ盤 / DLコード / 1LP] (BF111)_1506 [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/41ILtl+gukL._SL500_.jpg)













![空襲と文学[新装版] 空襲と文学[新装版]](https://m.media-amazon.com/images/I/41gP-+1OVXL._SL500_.jpg)



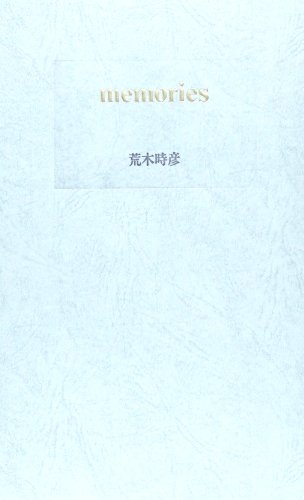

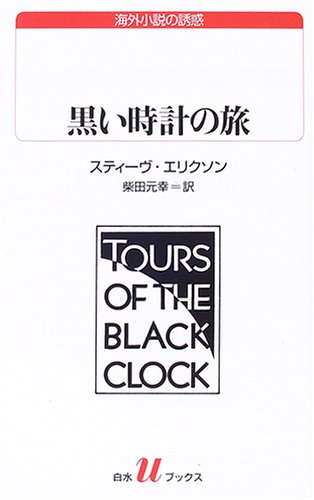












![【新ジャンル/第3のビール】本麒麟[500ml×24本] 【新ジャンル/第3のビール】本麒麟[500ml×24本]](https://m.media-amazon.com/images/I/51CREXm52zS._SL500_.jpg)



