振り返っていきます。
末法 !MAPPOU! いや凄い。去年も凄かったけど今年も人心の荒廃が加速度的に進行している。もはや末法 (MAPPOU)としか言いようがなく、ここまでくると、もうみんな頭がおかしくなってしまった、正気なのは俺だけなんじゃないか、間違いねえなっつうか平成に生まれてこのかた良い時代なんか一瞬たりともなかったろうがよ。なんか昭和の価値観?をアップデート(笑)とか言ってるクズどもがゴキブリみたいにわんさかのさばってきて俺はキレッぱなしでかなわんね。平成はどうしたんだよ。アップデート(笑)しなくていいのか?つうか昭和の価値観?を平成はそのままお通ししたんだな。言わねえもんな「平成の価値観」なんて、てめえらゴキブリは。要するに平成に生まれた価値観?なんて綺麗さっぱり消えてしまっても振り返ってみて特に差し障りのない、意味のないものだったってことだろ。そんな「無」しか産み出さなかった平成の文化(笑)だっておんなじだよなあ。全部ブルドーザーで片しちまえばいいんだよ元からゴミみたいなもんなんだからさ。あとアップデート(笑)な、ソフトウェアとエンジニアの区別もついているか怪しいカスOSのお前らにもわかるように書くが、あるソフトウェアをアップデートするファイルをそのソフトウェア自身が作るわけがねえ。作るのはソフトウェアの開発者たちで、お前らじゃねえ。アップデートファイルにバグがあるかどうかを報告するのはユーザーで、お前らじゃねえ、お前らはカスOSだってすぐ前に書いただろうが。お前らを使う奴らが不都合を発見して報告すると、開発者はもしかしたらバグ修正をしてくれるかもしれねえな。全部諦めて放置するかも知れんが。ところでどこに開発者がいるんだ?お前らがアップデート(笑)する価値観?を作ってくれる開発者の話をしてんだよ。アップデートに問題があったとき、開発者がユーザーに謝罪することはあるかもしれねえが、ソフトウェアに謝罪しているのを見たことがあるか?もうわかったと思うが、お前らみたいなアップデート(笑)野郎が真から腐ってんのは、悪を憂い善への進歩を願いつつ深刻な顔をするのが好きな癖して裏じゃスマ〜フォになったつもりで人間をポイ捨てしてやがるからだ。なめてんのか。いや知ってるよなめてんのは。人間の階層性を当然のように受け入れ、上部階層を盲目的に信頼し、同質性から逸れた連中(特に自分より「下」だと認識した奴ら)を徹底的に軽蔑することなしに、こんなゴミみたいな比喩が使えるわけがねえ。こういう、アップデート(笑)なんて言葉を使いたがる心性の構造をなんだっけ?昔の日本の政治思想史研究者か誰だったかが「超国家主義 」とか言ってたんじゃなかったっけか?覚え違いな気もするけどまあいいや。俺は悔しいよ。俺は中高くらいにネトウヨ 時代の頂点があって、それから後はそんな単純な悲しい世界じゃあねえよなあここはでもそれじゃあどういう世界なんだっつってウーンウーンいってんのに、お前らみんな数年であっさり超国家主義 まで行くんだもんな。ゴミクズの俺でもそんなことできねえよ。尊敬する。拍手してやろう。ぱちぱち。アップデートは世界的な流れで国家とか関係ない普遍的なものでーすはーいお前レイシスト !って言おうとしてるそこの脳が完全に腐っているお前に「世界国家」のことを一から説明するのは本当にだるいのでとりあえず貼っておくが、俺はお前らに何一つ期待していないので読もうが読むまいがどうだっていい。
つうか本当に色々なめてるよなお前ら。差別なんかど真ん中でそうだ。まず差別は文化なしには発生しねえ。文化に乗っかる教養に至っては差別を構成するために生まれるといっていい面さえある。「俺たちはお前らとは違う!」ってアレだよ。教養の目的をお前らがどこに設定しようが俺はどうでもいいが、大なり小なり糞のピラミッドであることに変わりはねえしな、どう設定するにせよその内在的な機能として教養は差別を生み出す。そういう教養の世界にベットしていくってのは、差別のグルーヴマシンに乗ってどんなダンスを踊ってみせるのかってことだ。「私は差別に加担 しない」とか真顔で言ってる小文化人志望者連中を見ると最初の頃はマジでびっくりしていたが最近はもう飽きた。お前らが手え染めてんのは加担するとかしないとかができるようなヤワなもんじゃねえ。ここは存在すること自体が差別であるようなフィールドなんだよ。「私は〇〇な思想のやつとは友だちになれない」みたいなこと言ってる奴見ると目ん玉が飛び出そうになる、嘘ついた、目ん玉はそうそう飛び出そうにならない。「吐き気がする」とかバンバン書いてるやつってその度にちゃんと吐き気がしてんのかな。俺は子供の頃思想で人を選別してから友達になるか決めようだなんて夢にも思わなかったし、もしかしたら子供の頃からそんなことをやってる高等人種(金髪碧眼)が、俺みたいな劣等人種(黄色い猿)が気づかなかっただけでいっぱいいるのかもしれないが、そんな何様なのか分からないことを俺がいい出したら子供の頃の俺や何より俺の友達を裏切るから、そんなこと口が裂けても言えない。あー、ここ読んでから勝手に自分の思想と似てると勘違いしてニヤニヤしながら近づいてこようとするゲス野郎は本当に遠くへいけ。俺は俺でないところで相当友達を選んでるに違いない。だから何で選んでるかが今もよく分からないんだが、お前らみたいなゲス野郎の顔を想像するだけで近づきたくねえと身体が言ってるんだ、遠くへいってくれ。お前らは多分義務教育課程で勉強が中途半端にしか出来なかったような奴らだろうから聞くんだけど、お前勉強がちっとばかし出来るぐらいのことでお前らより「ちょっと下」の連中からキモがられたりちょっと引かれてたりひどい場合だといじめられたりしたことなかったのか?あれはな、お前らが「ちょっと周りより出来る」ということ自体があいつらを傷つけたから起きたことなんだよ。……いやわからん、別に理由があるかも知れない、性格が終わっているとか、顔がキモすぎるとか、声のトーンが異常に上下するとか、身体の動きが悪い意味で人間離れしてるとか、そういうのかもしれない、そういう場合は……お前らよく今まで生き延びてきた、グッジョブ、これからもしっかりやってけ。……話が逸れたが、要するに存在するだけで人を傷つけるっつうことは全然ありまくりなんだが、なんか「口先手先の動かし方で回避可能です」みたいなキメ顔してる連中は全員終わっているということが言いたかった。お前らを見てると思うが文字を読んでるようなやつは本当ゴミクズしかいねえな!俺がゴミクズだから間違いねえ、やっぱり文盲がいねえ国は駄目だな。俺はSNS の中でもUIが徹底的に文字を嫌悪するように設計されていたTikTok に新しい人類の黎明を2%くらい期待してたんだが、YouTube もInstagram もFacebook ?めた?もパクりやがる上(圧倒的に文字愛者向けSNS であるツイッタが類似サービスを実装しなかったのは当然)、流れてくるもんを見てるとやはりここはどうしようもねえ……ここからめちゃくちゃ精錬されたルッキズム と「成功が全てを正当化する」式の「倫理」を兼ね備えた注目されたすぎる若者たちが世界中で「夢」に向かって進んでくんだろうな、みてえな薄暗い高揚感だけがヌワッとくるね。よく考えたら今は文字を読めることが文章を読めることにはならないということを完全に見失った文盲どころじゃねえ知的廃物どもが大手を振って闊歩してる時代なんだからその時代に産み出されもてはやされているTikTok 程度のおもちゃに期待するのは俺が愚劣以外の何物でもなかったということでしかねえ、ちっくしょう!とにかくお前らは俺に近づかないでくれ。俺の知らないところで勝手に生きて幸せな人生を送って死ね。何が人を傷つけてはいけない、だ。マジに俺は「人を傷つけてはいけない」が嫌すぎる上「〇〇はなぜ悪いのか→人を傷つけるから」になるともうテメエ殺してやる!みたいな勢いでカッとなるわけだがどうにも今まで言えなかった。ところで菊地成孔 のエッセイ本が出た。
最後の最後まで読んで、本当に自分が恥ずかしくなったよ。元からチキン野郎だったが、SNS にドはまりしていた間に俺は自分自身を際限なくスポイルし続けていたわけだ。ここまで読んで「こいつは人を傷つけて良いと言っている!」となったゲジゲジ は頼むから帰ってくれ。帰って全部の脚をセルフケアしろ。まず日本語の話をする。これは本で読んだことはないが多分誰かが書いたりしているのを見聞きした覚えがあることで、というか俺はここまでもここからもなにか新しいことは一切言ってないと思っているしそうありたいと思っているが、加害/被害という言葉には日本語の/における自由と運命がべったり貼り付いている。人間は台風の被害を受けることができるし、詐欺の被害に遭うことが出来るし、津波 の被害を受けることが出来るし、通り魔事件の被害に遭うことができる。被害という言葉は、その害を与えた要因が人為か自然かを区別しない。だが加害は違う。熊は加害しない。台風は加害しない。地震 も津波 も加害しない。加害することができるのは人間だけで、加害者になれるのは人間だけだ。加害者と被害者に広げると、必然的なもう一つの違いがある。人間は加害者になるかどうかを選ぶことができる。俺がお前を殺そうと思ったとして、数ヶ月に渡る準備をし、いざ決行日になって「や〜めた」と言うことは、主観的心理的 には不可能に思えていたとしても原理的には可能なわけだが、被害者は違う。被害に遭うかどうかを選ぶなんてことはまったく出来ない。誰が震災の被害に遭うかどうか選べたってんだ?ハザードマップ 見ろよだの海岸近くに住むとか馬鹿じゃねだの南海トラフ 来る来るとか何回も言われてんのにわざわざ危ない地域に住んでるとか笑だの顔してるそこのお前、オウムアムア に頭ぶつけて死ね。このムリさは言語の問題なわけで、こうやって日本語が、加害を自由と、被害を運命と、それぞれ根本的なところで結びつけている。最近俺は雨の日に道で滑ってコケて、十年以上ぶりに膝を擦って皮がずりって剥げて血がジワ〜って出てきたんだけど本当に嬉しかったね。俺の身体はまだ痛くなれるんだと思ってウキウキしながら電車乗ったよ。こんな一瞬ばかりじゃないだろうが、傷の意味だって時間が経てば変わっていってしまう。初めての失恋の質感が当時からウン十年経っても変わらないやついるか?いるかもしれねえ……『コレラの時代の愛 』とか、いやあれはもう振られても諦めないとかそういうレベルの話ではないド迫力だった気がするけどとにかくお前はすげえよ、幸あれ、またいつかやってくるかもしれない最高の運命に渾身の加害をやったれって思うがまあ大抵そうはならねえだろ。言葉を使う宇宙ゴミ の俺たちにできることは与えられた世界に対して言葉を何度もかけなおすこと、世界からの言葉を受け取りなおすこと、そうやって時間を生み出していくこと、時間は絶対に与えられたりしない、そういう風にしたがる奴らが昭和やら平成やら令和やら西暦やらヒジュラ暦 やらユダヤ暦 やら革命暦 やら何暦やら何暦何暦何暦!暦ってのは権力の中でもかなりマキシマム、時間を支配として構築しようとする力の現れだ。まあ誰が悪いって話でもねえ。力ってのは個人のレベルに収まるようなもんじゃねえからな。知ってるか?魔法は本当にあるんだよ。言葉を使う者たちが集まるとき、あるいは人々の言葉が集まるとき、全体が部分の総体を超える、その場所で魔法、っつうか目に見えない力が分厚い雲の上の風みたいにうねりまくってるんだ。呪文って文だ。自然法 ってあるが多分自然にも法が書かれてる、ってか天文学 ってすげえだろ!今じゃ天体物理学なんてさびしい名前になっちまったが、昔の天文学者 と呼ばれてた連中、あの中には多分マジに天の文が読めるやつがいた。ガリレオ は、あいつのことはまだ掴めてない。天の文を読むことを比喩にしちまったような気もするが、手のバイブスのことを考えるとあながちそうともいい切れない。
ブレーデカンプのこれに取り上げられてたガリレオ のニューヨーク手稿(だったっけな?)は偽物だったことが後に判明した、みたいなことを読んだが天文……?ああ暦の話だった。俺たちは暦の外側に行かなきゃいけない。時間を取り戻すってのは可処分時間を増やすためにFIRE……みたいなみみっちい話じゃねえ。自由!自由!自由なんかいらないって思ってるやつの作ってるもんなんかどうでもいい。つうか端的にゴミだと思ってる。俺はお前の作ったもんで俺を傷つけろ、ガッと持っていってくれって言ってるんだ。ああそう、これはあれだ、SMに近い。俺は中学生の時から団鬼六 が好きだった。どこまでもマンネリ、しかし行けるとこまで行く(アイツ結構な頻度で終盤巻くからな)、「聖性とエロティシズム」みたいな気取った方へ足を伸ばす気にもならない俗の力。読者が面白がってくれるならエッセイでさえ平然と話を盛り嘘をつく豪放なサービス精神。団鬼六 の官能小説の中では、調教する加害者のSと調教される被害者のMの構図が、いつの間にか調教させられる被害者のSと調教させる加害者のMへとスッパリ逆転……するのでもなくぐしゃぐしゃに混濁していく。団鬼六 はいつもそうだ。(本当に?)それしかないのか!素晴らしい!SMは日本語の加害-自由-支配と被害-運命-服従 の連関を保ったまま無茶苦茶にすることができる。受動態と能動態を駆使して、意味論的力と統語論 的力をバキバキにクロスさせて。もちろんSMとSMプレイの間にある「プレイ」の差を無視することはできない。だがこのうんざりするような日本語をぐっしゃぐしゃにできる可能性がこの世の中にあるというだけでもめっけもんだ。でも自分はやっぱり人を傷つけたくない、それはわかる、というより共感している。考えるより先に身体がうんうんという。俺にだってそれくらいのことは起こる。だが同じくらい俺の身体は正反対にいきり立ってもいる。「傷つけることは悪かどうか」じゃねえ、その根っこがおかしいんだ。全部無茶苦茶にしなくちゃいけねえ。もし俺が誰かが誰かに傷つけられたところを見て、そこに悪を感じ取ったとするなら、悪の理由は誰かが誰かを傷つけたことそれ自体にはない、と考えるだろう。そいつを超えたもっと大きな力のことを考えるだろう。魔法の話はしたな。例えば俺はここ二年くらいで「ヘイト」や「トランスジェンダー 」や「多様性」や……といった文字列が入った文章からはほとんど例外なく邪悪な影を感じるようになった。俺は文化人類学 には全く詳しくないが、どうやら「妖術」と「邪術」という素晴らしい区分を考えついたやつがいるらしい。黒魔術 は黒魔術師じゃなくても誰でも使える、というか使うつもりもない、使えると思ってさえいないのに発動してしまうことがある。黒魔術に黒魔術で対抗しようとしてどうするんだ?そんなもんはねえってどうしても言うんなら、この本、伊藤計劃 の『虐殺器官 』に出てきた「虐殺の文法」の発想源の一つだろうな確証はないがと俺は思っているんだが、そこに俺が「黒魔術」と呼んでるうねりの例がいくつもある。例によって無理に読む必要はねえ。今だとなかなか買えないしな。今読むと1ページ目から慄然としてくるが。
第三帝国 の言語は、新たな必要に迫られて、引き離すことを意味する前綴り ent の使用をいくぶん増加させた。(この場合それが完全な新語の創造なのか、それとも専門家の間では周知の用語を一般の言語へ取り入れたのかは、どれも明らかではない。)たとえば、窓は空襲の危険に対して遮蔽されねばならなかったので、暗幕を取り除く、、 (ent・・・ dunkeln)ことが日課 となった。
(中略)
現代のもっとも重要な課題の総括的名称として、これと同じように作られたひとつの語形が一般に用いられるようになった。すなわち、ナチズムによってドイツはほとんど壊滅したのだが、この重症を癒そうとする努力は今日、非、 ナチ化(ent・・・ nazifizierung)と呼ばれている。この醜悪な言葉が定着することをわたしは望みもしないし、信じてもいない、それは目前の責任が果たされるやいなや消滅し、もはや歴史的な存在にすぎなくなるであろう。
だからというんじゃないが「自分の作ったものが悪影響を与えるかもしれない ことに対する責任をあなたはどう考えてらっしゃるんですか!はっきりしてください! 」とか聞かれたらブン殴る以外の回答が思いつかない。……いや俺はチキンだから殴るどころか激昂もできないまま明後日の方向に走り出す可能性が高いがそれはともかく俺は国家と違ってバカやクズどものパパじゃない。それでももしお前らがどうしても俺に、自分が独裁者になり、一度でもSNS を使ったことのある人間を全員処刑する執行命令書にサインし、自分も使っていたことを失念してうっかり自分も処刑される妄想を何度かしたことのあるこの俺に「製造物責任 」を取れというのなら、回答はこうだ。まず独裁者になり、俺の創作物に触れたことのある連中を全員処刑する。しかしまだ安心は出来ない。そいつらが俺の創作物について誰かに話したかも知れない。というわけでそいつらの家族友人恋人同僚知人を全員処刑する。しかしまだ安心はできない。SNS に書き込んだかも知れない(お?)。あれは不特定多数に見られるが、誰が読んだのかこちらでは確かめようがない(お?お?)。そこで一度でもSNS を使ったことのある人間を、俺を除いて(っしゃあ!)全員処刑する執行命令書にサインする。まだ安心はできない。残った俺以外の人間も全員処刑する(!?)。そして世界でたった一人の人間になった俺は、何を思っているのかもよく分からなくなりながら、全ての病気にかかったのち餓死する。当然これは冗談だ、俺は政治にまったく興味がない、独裁者になりたいと思ったことはありません、信じてください。まあそれはいいが、本当にお前らは人に「お前はどう思っているんだ!」とか「黙っていることは敵に加担することです!」とか言うのが大好きだよな。皆様は当然教養がおありなのでロラン・バルト が「ファシズム とは何かを言わせまいとするものではなく、何かを強制的に言わせるもの」と書いているのを当然知っていて、「それは言語活動の遂行形態としての言語の話で政治的な実践の話ではないので自分たちのやっていることはファシズム ではありませ〜ん!」ということでやっていらっしゃるのであろうが、俺には意味が分からんけどとりあえず俺の知らないところで勝手に幸せになって長生きして死んでほしい。こうして改めて書いてみると文字愛者御用達SNS たるツイッタはファシズム の増幅装置でしかないが、とはいえInstagram を開くと最近はThreadsに誘導しようとしてかなんかバズりつつあるThread?Threads?がサジェストされるようになっていて、そのすべてがことごとくカスなので本当に俺の直感は正しすぎる。ツイッタからの大移動が取り沙汰されたときに俺はmastodon のアカウントを消したからな。こんな劇物 はツイッタだけで十分。物作りの責任は「こんなん作ってみたが、俺出していいのか?」とか「出すぞ!……でも、何か引っかかる……」みたいなところが精一杯だ。責任と階層的社会観は継ぎ目が見えないほど癒着していているから分かりにくくなっているが、本当は人間にそもそも責任なんか(自己責任さえ!)取れない可能性がある。それでも責任という言葉へ向き合うなら、黒魔術のことを忘れんな。俺たちは落合陽一が出てくるずっとずっと前からみんな魔術師だったことを思い出そう。文字を綴ることと呪文は同じspellだ。やべえ激烈に劣化した松岡正剛 みたいになってきちゃったかもしれねえ。しかし表現の責任、ときたらアレだよな、「表現の自由 」も最近えらく腐臭がキツイな。そら俺だってポジショントーク をさせてもらえるなら大事だって思うさ。書いたもんにゴタゴタ言われるのは構わんが、いやブチギレたりズーーーーーンって刺さったりマジどうでもいいなって思ったりするだろうけど、「書くな!」と言われたら「じゃあ殺して良いな?」ぐらいには脳直でいくね。書いたはずみで金がもらえたりしたらこれ以上ないくらい最高だが俺は「(俺の納得できないこと)を書いてください」と言われてハイッ!つって即書けるほど賢くも器用でも恥知らずでもねえ、んだから最大限の「表現の自由 」を当然求めるってことになる。できることなら原稿料共同体からパージされたくねえしな。何が「みなさん」にとって「引っかかるか」「アウトか」なんて俺にはよう分からんしこんな考え方をまずしたくねえよ、監視社会以外でどうしてこんな発想をさせられるところに追い込まれることがあるんだよ、何が「俺」にとって「引っかかるか」「アウトか」には敏感でありたいと思うがポジショントーク をやめるならそもそも「表現の自由 」なんてものは国家やら宗教やら人間の上階層として現れ行使される権力があり続ける限りは原理的に存在しねえ。日本国憲法 によると国家の主権は国民に存するらしいから、日本国の主権者たる国民が存在しなくなるまでは、少なくとも日本国において「表現の自由 」は存在しねえことになる。異常に警察権力と自己弾圧が好きなこの国民共 の習性から考えると、表現それ自体犯罪のポテンシャルからし か現れないことがより一層、実践的にはっきりしてくる。今ここを読んで「そうかやはり表現はそれ自体犯罪的だからオッケー!」っつってクッソしょうもないヘイト文やらゲボみたいな動画やらドバドバする、「犯罪的な表現」と「表現は犯罪的である」の区別のつかねえ奴はどうしようもねえから黙って滝行にでも行ってくれ。差別的かつ犯罪的であることが表現することの逃れがたい基底である、そういう世界から俺は出発せざるを得ない。俺は表現の自由 のことを考えるときにいっつも「詩人追放論」のことを考える。
VIDEO youtu.be
上の動画でプラトン の詩人追放論について高橋睦郎 は、プラトン が理想国家から追放したかったのは「詩的なもの」であって「詩」ではなかったんじゃないか、という風に自分勝手に思って読んでいる、「詩的なもの」は「本当の詩」から最も遠いものだ、というようなことを言っていてそれは確かに俺も思わないでもない、明智 の人プラトン が「国家の法としての」ホメロス というものを疑っていたんじゃないか、というのもそんな気はする、が、というか俺はプラトン の『国家』を未だに読んでいないので、こいつ一体何なら読んでるんだ?と自分で思うわけだが、でも俺はやっぱり文字通り「理想国家からは詩人を追放すべきだ」とする方がしっくりくるが、そのままではなく対偶をとるように読む、つまり、詩人が生まれてきてしまうような国家は理想国家ではない 、という形を今のところ一番受け入れている。本編を実際に読んだらガッカリするかもしれんな。冷静に考えて、この世のありとあらゆる悪の原因が詩人であるわけがない。詩人を絶滅させさえすれば理想的な世界がやってくると思いますかアナタ?なんで百歩譲って詩がいくつかの個別の悪の十分条件 であったとしても、ここが理想国家ではないことの十分条件 であるとは認められない。その程度の悪であるなら、「詩」を書ける「本物の詩人」ならたしかに理想国家内に残しておいてもいいような気がする。が、対偶であれば話は全然変わってくる。あらゆる詩はその内容以前にそれが詩であることそのものによって、ここが呪われた世界であることを告知する。詩人はそれを証するものとして、「国民」からは呪われるものとしてある。これが詩に限られることなのかどうか。ユートピア に芸術は必要ない。必要があるなら、「ここではないどこか」が表現されようとする力がまだそこにあるとしたなら、そこはユートピア の名に値しない。しかし現状はあまりにもそこから遠い。「あらゆる犯罪は革命的である」と合体させてみてもいいが「あらゆる表現は革命的である」としたらもう表現というのは革命的でもなんでもない。俺も腐臭のする言葉遣いをしはじめているな、糞が!ここに外側はない。どんづまりや!ああ生まれたときからやった!まあ「自由」や「人権」より「安全」と「安心」が好きな奴らに支持された世界が今しばらくは伸長し続けるだろう。カスみたいな「アップデート」によってカスみたいな亜インテリ気取り及び労働者階級気取りの無脳「市民階級」共がニュースの一つ一つに一喜一憂しながら世界を「善導」してくれるだろう。実際のところ俺にこの流れを止める気はねえっつうかそんなことは俺個人のレベルではできねえしそれ以前に今止めようとしてる連中から漂ってくる邪悪さは「アップデート」連中の邪悪さをわずかに上回っているから近寄りたくもねえというのが正直なところだ。安心しろ、俺はお前らを直接どうこうするつもりはねえ。お前らがカスみたいなもんを書いて地球の資源を浪費するのはSDGs に反してんじゃねーの?????ってたまに思うぐらいのことだ。「安全」や「安心」だって「人権」が要求することの一つだ、っていいたいやつもいるかも知れないが、「人権」はそれへ向けて構成されなければありえなかったフィクションだが、「安全」や「安心」を構成するのに「人権」は全然必須条件じゃないってことを忘れないでほしいね。当然「自由」も同じだ。どんな存在に「安全」や「安心」を保障してもらおうとしてるんだ?噂だが、なんでもどっかの国の大統領に「ミスター安全保障 」と呼ばれていたナチの正統後継者がいるらしいな。まあ彼一人が特別邪悪って話でもなかろうし彼の国民が全員邪悪って話でもないだろう。いや実はそうなのかもしれないけど俺はそうじゃないと思うよ。これも黒魔術の話だと思う。ハイデガー の言ってたことが当たってるとしたら、俺たちはみんなゆっくり時間をかけてナチの後継者になっていったということになるだろうな。なんでこんなひでえ世界になったんだ。書簡体小説 の誕生を通じて、階層間を超える共感が生まれ、そこから人権が創造されるための土壌が生まれたってリン・ハントの書きっぷりにえらく感動した数年前の俺を返してくれ。
ああ全部殺したくなってきた……いけねえ俺が俺だけが正気なんだ思い出せ思い出せ、なんだっけ、俺が超絶劣化した松岡正剛 になりつつあるところまで思い出してきたぞ。ちょっとアヤしいくらいでいいんだよ、人生は科学じゃねえ。どんな科学も程度は様々にしろ脱属人化した集合的な蓄積的営為で定命の者たる人間の世俗的な祈りの最たるものだが、どんな人生もそいつが死んだらそれで終わる、そいつの経験や記憶はそこで途切れる。イアン・スティー ヴンソンの『前世を記憶する子どもたち』は色んな意味で面白い本だが、これを読んでいると、たとえ生まれ変わりがあったとしても前世の記憶は完全な状態で人間全員に引き継がれているわけじゃない、しかも前世の記憶は5歳くらいから失われたり封じられていってしまうこと、そして前世の記憶が完全にあるなら前世の前世の記憶、前世の前世の前世の記憶、……が当然内包されているはずだが、蓄積的な人生の相続をそこまでやりきってるやつはいねえってことがわかってくる。
科学的な人生ってのは楳図かずお の『漂流教室 』に出てくる未来人類みたいなヤツの人生になるわけだが、俺は願い下げだね。アイツらは「旧人 類」の記録映画を見る。余白にノスタルジー しかなくなっている自覚がないだけだが、あのような永遠の生に残されるものはうつ病 だけだ。旧人 類の俺たち、生き残った者たちが引き継げるのは、死者と関わり合った記憶に結びついた、そいつへの思いしかない。こう書いてみるとそれも言い過ぎでやっぱり死者からは何一つ引き継げないのかもしれねえ。いや違うな、むしろ死者と生者とパッキリ分けられるような記憶がそもそも存在しないんだ。そいつがいなければありえなかった記憶は、俺だけの記憶じゃねえ、もちろんそいつだけの記憶でもねえ。それは宇宙の記憶で、俺やそいつやその景色は、宇宙の記憶を呼び起こす鍵として存在しているのかもしれねえ。人生を科学の言葉に合わせて裁断しようとするプロクルステスの寝台 みたいな野郎が望んでる人間像は、快と不快を入力するスイッチが付いていて、イコールを押すと対応する表情(目で見て分かる )や言葉(聞いて分かる )が表示される電卓みたいなもんだ。任意の語やカットを使用あるいは禁止し、文字列やシークエンスを編成したものを電卓に投入すると、画面に「エンパワメントされた」「ケアされた」「傷ついた」「おしっこ」などが返ってくるようなプログラムを組めるということになるわけだ。俺は文学でも音楽でも映画でもなんでも、自分がエンパワメントされた、ケアされたと感じたことは一度たりともねえ。まず言っていることの意味が全く分からん。……いや気づいてないだけで実はあったのかもしれねえが、それは「その時、その場所で」であって、いつでもどこでもおんなじ効用を発揮する芸術なんてねえ。もしそんなものだとしたら芸術は医薬品、つまり厚生労働省 の所轄になるだろ。っていうかお前らは芸術が文部科学省 の管轄か厚生労働省 の管轄か法務省 の管轄かってことにしか興味がないんだろうが。いいか、文学部が後生大事に抱えて「守ろう」と息巻いている文化は全部もう死んだ、お亡くなりになった、完全にくたばった、御逝去あそばされた文化だ。大学に入ったあと一瞬文学部に入ったほうが良かったかな……と思いその後授業を覗いたり学部棟を歩いたりした結果爆速でこんなところに入らなくて本当に良かったと思った俺が言うんだから間違いない。まあ経済学部に入ってよかったかというとそれは別の話になるわけだがやっぱ人間なめてんなこいつら、ブチ殺してやる!何が反出生主義だ!幸福の絶頂に至った瞬間に「生まれてこないほうが良かったー!!!!!」って絶叫できるやつを連れてこい、そいつの話なら聞いてやっても良い。子どもを電卓だと思うようになった連中が「製造物責任 」のように「本人」の未来の「幸せ」やら「不幸」やらを査定しながら子どもを「生産」するかどうかを「計画」する。少なくとも「家族計画」なんて言葉が生まれた頃には俺たちは狂いはじめている、ホントのところもっと前からだろうがな。人生と科学どころか、人生とプロダクトとの区別までついてねえ。やべえ正気であることを思い出したかっただけなのに小学生の頃まで思い出してきた、俺は小学生の時、家に帰ってくると親が給食民営化の反対運動があって署名に俺の名前も書いたと言ってきて即バチギレした。俺に何も知らせず?勝手に?俺の?名前を?書いた?多分俺がバチ切れることを予想だにしてなかったのか「いやだって給食が民営化されるとこんな悪いことが……」みたいなことを付け加え始めたのでもっとバチ切れし、これ以降俺は人間と社会、「この社会」じゃねえ社会だ!を信頼できなくなる。俺の名前は道具だったことが分かったわけだからな。大学に入るまでに文学の土台になったのは団鬼六 と西村寿行 、もはや粗製濫造に近い西村寿行 の卑俗で暴力的な、そしてなにより膨大な量の文学から俺は「クオリティがどうとか知らんわ、とにかくやるんだよ、書きまくればええ」とぶん投げていい勇気をもらった。いいのかそれで?いや粗製濫造といっても例えば『地獄』は今読んでも「こんなことをして良いはずがないだろ……」というぐらい無茶苦茶な出版業界内輪ネタで最高だが、そして安部公房 。単純に『密会』がおもしろエロすぎてハマった。文学っぽい文学でもエッチなことを書いて良いんじゃん!あとすごすぎるだろ最後の最後。こうしてみると俺って小説の判断軸がエロいかどうかしかないんじゃねえのか?コンビニで18禁雑誌の中身を想像してドキドキしてるガキ(絶滅危惧種 )となんにも変わんねえ!ちくま学芸文庫 や講談社学術文庫 どころか、岩波文庫 の存在すら大学に入るまでまったく知らなかった。それまでに読んだ「らしい」本は高校生の時図書館で手に取った新潮文庫 旧版のニーチェ 『善悪の彼岸 』。30ページくらい読んで挫折した。それまで自分に読めない日本語はないと思っていたのに、そこには日本語で書いてあることだけは分かるが自分の力では一切読むことのできない文章があって、俺は頭をトンカチで殴られる。それからいよいようようよ曲折して最近はハイデガー 、ヴィトゲンシュタイン 、荒川修作 の三人のことをぐるぐる考えたりしているが、そこに至るまでに東日本大震災 があって「がんばろう日本」やら「絆」やらいくつもの言葉が数年をかけてゴミクズにされていって俺は「絆」やら「連帯」やら「共生」やらといった言葉を一切信用しなくなる。荒川がたしか誰かを評して「『共生』なんてくだらないことは言わなかった」って喋ってた(誰の話か忘れた)のを読んで衝撃だった。おれは震災を経由しなければそうはならなかった。荒川はもっと原理的にその荒涼とした地点から、しかし希望を捨てることなくやっていってた。ハイデガー の「共存在」も、あれは世界内存在としての現存在のありかたとして、「超越論的」という言葉は不適切にしても「共」を実質的なものからは遠ざける形になってる。ハイデガー の書いてることには最初から最後までさびしさがある。誰がさびしいとかいうわけではないさびしさが。現在という状況下で、およそ共生など考えることさえ出来ない、しかし……といったうじうじしたものも感じるがとにかくハイデガー もあんまり「共生」という言葉のイメージからやっていくということに関心はなかったろう。ヴィトゲンシュタイン に至ってはもう共生がどうとかいうステージに住んでいない。20世紀に入ってから「詩的な」文章を書く哲学者、思想家はそれこそハイデガー やらベンヤミン やらデリダ やらドゥルーズ やら……やらドバドバ出てきたんだろうが、哲学自体が詩でもあるような人間となると今のところヴィトゲンシュタイン しか出会ったことがない(読んだことはないけど噂を聞く限りベルクソン もちょっとその気配がある気がする)。とにかく『色彩について』は最高で、論理と世界という直接には繋がらないかにみえる2つをつなぐものとして「色」を見出す、色を見出すってすごい冗長な雰囲気あるが、俺は最近になって、俺が詩をやりたいとか、これは詩だなって感じるのは、最初から全部そこにあったものを見出す営為なんじゃないかっていう気がしてきて、これは別に詩に限った話でもないけど、荒川洋治 が「キルギス 錐情」の冒頭で「方法の午後、ひとは、視えるものを視ることはできない。」とブチ上げたわけだが日本語現代詩史を引っ張り出さなくてもそのままにそうだよなと思う。視えるものがちゃんと視えているってのは超難しくて大変なことだ。大概色眼鏡を掛けてるってことをすっかり忘れてしまうほどに色眼鏡と目は癒着しきっているし、その色眼鏡はどんな色にしても時を経るごとにくすんでいってしまった、多分「方法の午後」ってそういうことなんじゃねえかって俺は思うんだけど、多分外すことは出来ない色眼鏡(イデオロギー ってそれを認識した程度のことじゃ脱出なんてできないから大変なんでしょ)、当然色眼鏡だからそこには色があって、色があるならそこには色独特の論理があるんだってこと、自分が掛けてしまっている色眼鏡の論理を見抜けるかどうか、そして色眼鏡を拭き直すことはできるか、そういうことが詩をやるにしても別のことをやるにしても大事なんじゃねえのって俺は思う。ともかく本当に目の前にあることへ最後の最後に帰ってきたヴィトゲンシュタイン って男は半端じゃねえ。
んで『色彩について』を読んでてもう一個思うことだがこいつ全然「想像力」に頼ってねえ。俺は「想像力」をやたら称揚するのが大嫌いで自分の詩でも「想像するな 相続せよ/富んだ無理でくらせ」って書いたわけだが想像力もやっぱり力なんでね、個人の意志で統御できるようなもんじゃあねえだろって思うんだよな、こちとら筋力すらコントロール できてるか怪しいってのによ、想像力だぞ!影も形もねえ!そして「共感」の匂いもヴィトゲンシュタイン にはまったくしねえ。俺はここ2、3年は「想像力」や「共感」のない場所から始めるほかなかったような!文学が!最高です!ってバイブスになってて、例えばベケット にはそういう雰囲気が濃厚に感じられるんだけど(あの小説群が想像力で書けるとは思えないんだよね)、そういう人たちの文学は「想像力」とか「共感」とかの欠如を埋めたい、埋めよう!とする方向には行かなかった、いや、何が欠落したのかも思い出せないような欠落の哀しさや寂しさのオーラみたいなものはちょっとあるけど、むしろそれをきっかけにして「想像力」や「共感」の縁を掴んでくるセンスが生まれてくるはずなのに、その手をそちらには伸ばしていかないように見える、ってところにデカさを感じる。ベケット はたぶん身体もデカい。友人のPとたまに文学者の身長の話をする。身長によって世界を見る基準線に高低差が生まれるんだから、世界の見え方だって違うはずだ。うわあっカフカ の身長ってどうなんだとGoogle先生 に聞いてみると(ベケット のことは教えてくれなかった)、真実を教えてくれた。
いや実際に正しいのかは一切知らんが、俺はやはりカフカ もデカかったと思う。身長182cmの男があのような小説を書いている、こんなに素晴らしいことがあるか。他にも真の検索を試みている人間がいるようで嬉しいがそれはそれとして、誰かに共感している感覚があるのに更にそこに想像力を働かせようってのは俺には冗長に感じられて面白くない、その共感をみなぎらせたまま想像せずにガーッってやる方が一周回ってより芯を食えるんじゃなかろうか。想像力を使うなら自分の一番共感できないこと、一番嫌いな奴に対して使うのがいい。そこに行かねえ行く気もねえのはチキン野郎、先回りした想像力に国境線を引かせてその内側から一歩も出ねえチキンホークだ。小説家の誰だったか(高橋源一郎 だった気がするけど違うかも知れない)、「当事者のことは当事者じゃない人間のほうが書ける」って言ってて「それだ!」と思った。というかそれはおよそフィクションに手を染めるということの倫理を成り立たせるために必須の信仰だと思う。これに頷けないなら私小説 でさえ書くべきじゃない。書いてる自分は書かれている自分の当事者だと本当に思うか?小説の中の登場人物は存在しないんだから気にしなくていいと本当に思うか?ならなんで登場人物に働かれる不正に憤れたり悲しめたりするんだ?不正を被る対象としての人物が存在しないなら「〇〇に不正が加えられている」は命題として成立しないんだから憤ったり悲しんだりするのはおかしいんじゃねえのか?感じてるフリしてんのか?ケンダル・ウォルトン の『フィクションとは何か』じみてきてないか?あれは面白いけどどこまでもフィクションの周りを巡ってばかりでフィクションには到達しないカフカ の「城」じみたところがないか?もっと宇宙的に、ヴィトゲンシュタイン の「色彩」のように考えるほうがいいんじゃないか?
誰ひとりいないような小説だってきっと書けるし、なんなら別にフィクションをやる義務なんかないんだからノンフィクションに向き合っても良い。とはいってもノンフィクションだって同じ葛藤にぶち当たるはずなんだけど。まあいいや、お前らはお前らで勝手に戦ってろ、俺は戦ったりしない、ただ侮蔑し、嘲笑し、「この戦争」が終わったあとで「角川文庫刊行の辞」みたいな、冗談としか思えない駄言 が二度と口にされることがないよう、文化の死体でいっぱいになった耕作放棄 地を海水でなんども揉み洗いする、バイブスとしては読んだことないけど「虫けらどもをひねりつぶす」ってことでやっていく。ああ来年はセリーヌ を読もう。あと結局積んだままにしてしまったリュシアン・ルバテの『残骸』を読もう。世界に何一つ納得いかないで一人ガンギまってしまった奴らのことしか信じられない。今年は本当にひどい、生誕以来最悪の年、反物質 のボージョレ・ヌーヴォー みたいな年だった。オタク的なものが何もかも曖昧にされたまま隅々にまで拡散し尽くしてだいぶたった。革命の季節が終わったあとでなおこの世界の気持ち悪さと戦うために何が残せるのかとおそらく意識的にか無意識的にか考え、俗流 ニーチェ 主義をオタクに重ね合わせることで高貴な少数者の抵抗を試み、はやくもゼロ年代 (気色の悪い表記)には挫折を宣言し、それでも今なお自分が深く関わった「オタク」への責任を果たそうとしている(ように見える)岡田斗司夫 のことを考えたりしてしまう。色々言われるけど本来あの人SFオタクであろうに、YouTube ではそういう素振りはほぼ見せずジブリ やらガンダム やらの話ばかりする、それは、居場所がないことへの不安を持った人々に、「これさえ知っておけばとりあえず『オタク』というアイデンティティ は手に入るだろうし、共通の話題を持って他人と繋がれるようになることもあろう」という、オタクの延長というよりかは活動家の後始末じゃねえのかと思うのだが、それはそれとして天皇 は支配階級としての最低限の教養を持つこと、そして(おそらく)生存戦略 も兼ねてオタクでなければならなかった、昭和天皇 も平成天皇 も今上陛下も研究者としての側面を持っていたが、バリバリの研究者になってしまってはとても天皇 ではいられない。ということで「象徴天皇制 」においてオタクはそうでない人々に比べより天皇 に象徴されていると言えるが(暴論1)、さらに歌会始 を見れば分かるように、天皇 は短歌の頂点にも君臨している。このことから「象徴天皇制 」において歌人 はそうでない人々に比べより天皇 に象徴されていると言え(暴論2)、よって「象徴天皇制 」においてオタクの歌人 はそうでない人々に比べさらにさらに天皇 に象徴されていると言える(暴論3)。さっき「この戦争」と言ったが、俺は情熱大陸 に木下龍也が出たあたりからこの国は少なくとも感性のレベルにおいて戦時中に突入したと認識している。ある詩人が「詩が日本で一番売れたのは戦時中」と言っていたのを思い出す。「愛国百人一首 」なんてものもあった。もちろんこれらの歴史を知っているはずの人々がそっくりそのままの形で歴史を繰り返すということは到底考えられない。次来るナチがナチの装いでくるはずがないのと一緒だ、そんなことをしたら政治生命がどうなるかなんていうまでもないからな。文フリ東京は出店数も客数も増加がすごいことになり続けている。もう来年からは行かないと思う。今年会場が逆だったら普通に人間の密度がヤバすぎて人酔いでグロッキーしていた可能性が高い。あと瘴気が強すぎる。身体が「ここにいてはいけない」と言っている。別に文フリだけが特別じゃない。内容云々ではないところで、文学的なものがとても嫌な盛り上がり方をしている。それはともかく今の俺にはもう現在の短歌は読めない。1ページ開くだけで大抵の場合ちょっと気持ち悪くなってくる。もっと言えば最近は帰り際とかにデケえ本屋に寄っても(都市生活者の特権)表紙見るだけでげんなりしてくるので短歌に限らず文学はほぼ買わない。研究者でもない友人のQは昔「本って好き嫌いとかじゃなくて義務で読むもんじゃないんですか?」と言い切っていてその峻厳な姿勢に感銘を受けたことがあって、好き嫌いでしか基本的にやらない俺もしゃあなしやるか、と目だけは通したいと思っているがまあ俺は惰弱なので義務じゃなくて義務感が精一杯でそれじゃあつらいものがあるし、金は有限なのでマジ選びしなくてはならない。そうなると優先度として今の短歌はゴリゴリ落ちる。現代詩文庫『三好達治 詩集』に収録されている鮎川信夫 の評の中で三好は「自然詩人」と呼ばれる。「自然詩人」の拠ってかかるところは抒情、それも「短歌的抒情」だ。正確に覚えてないけど最終的には「日本が駄目なままなら三好達治 的なものも長生きするであろう」みたいな書きっぷりでそこまで言う!?と思うし俺は鮎川は詩は確かにすごいとは思うけど息がつまりそうになるからそんな好きじゃないんだが確かに今ここはとても気持ちの悪い日本語でいっぱいだ!全部片してやる!ブルドーザーをダースで持って来い!と思ってしまう。
その一方で、おいお前「正気なのは俺だけなんじゃないか」とか言っているが冷静に考えてみろ、「自分以外が全員狂っている」と、「『自分以外が全員狂っている』と言っているやつが狂っている」可能性、どちらが高いかな?お前は小さい頃から手前勝手な白黒をめちゃくちゃはっきりつけたがる。その性向がどれほどの場面で酷い間違いへと自分を、周りを巻き込んでいったか、身にしみているはずだろうに。お前は長々と呪詛の言葉を書き連ねたがはっきり言えば黒魔術についてしか喋っていない。自分が白魔術師にでもなったつもりか?お前もしっかり黒魔術師じゃないか。確かに黒魔術師はお前だけに限らないかもしれない。虹彩 の色は多々あれど、瞳孔は皆黒いことを忘れていないか?俺たちはみんな黒い穴の底に映った世界を見ているということを見ることができないんだ。人が黒魔術から逃れがたい理由の可能性の一つとして、忘れないでいてほしい。そしてお前は無理をした。お前は中学生を終えた頃ぐらいから、自分の原動力が「自分でもわけの分からない怒り」しかないことを悲しんでいたじゃないか。お前はまた「怒り」で走りきろうとしたが、全部吐き出すことを優先して文体も構成もめちゃくちゃになった文章、そのいくつかのピースではもう怒りを維持することができなくなっているのが丸わかりだ。今のお前の怒りは二万字もたないんだ。怒りでしかやっていけない時期というのは確かにありうる。だが怒りだけでは持たない。自分で気づいていることじゃないか。次。お前は自分がネトウヨ から脱したかのように書いているが、本当にそうか?いや、正確にはお前は自分がいまネトウヨ じゃないのかどうかさえわからなくなっていて、そのことをはぐらかすようにしている。お前は最後の方でうっかりしたように「陛下」と書いた。お前は高校生のときに初めて、遠目で、ガラスの向こう側だったが、そこで生の平成天皇 と皇后を目撃する。夏だったかもう忘れたが、陽差しの濃い日に合唱団員として「文化事業」に駆り出されたお前は、そこでやはり直立したまま微動だにしない二人を見て、高校生なりに感動する。「エアコン効いてるだろガラスの向こう側は」と後に自分で思ったとしても、やはり老体の不動に感動したことは消えなくて、三島由紀夫 もやはり直立不動の昭和帝の話をしていたことを知ったりして、お前はこの制度にどういう言葉遣いをしたらいいか、いまだ考えあぐねている。「天皇 制」を「打倒」する、という言葉がまだ奇妙な響きに聞こえている。あれはいったいそういうものなんだろうか?日本人の中でクズじゃないやつ、有徳の名に値するのはもはや天皇 だけなのではないか、という妄念が強まった時期は、お前が「ネトウヨ 時代の頂点」と書いた時期よりもあとのことではなかったのか?「天皇 制」は「打倒される」のように打倒されうるものなんだろうか?お前は「象徴天皇制 」という言葉に未だに新鮮なおののきを覚える。まだ戦前の天皇 制のほうがシンプルに思える。はっきりしているのは、お前は他人から「あなたは今でもネトウヨ ですよ」と言われても、「あなたはもうネトウヨ じゃないですよ」と言われても、「ちがう、そういうんじゃない、そういうことじゃないんだ」と言うしかないだろうということだけだ。目に入った文字を好き放題摂食してネトウヨ になったお前(文字単位の刺激に反射で激昂する癖はTwitter で悪化したようだな)、「平成」に生まれたお前、お前は本当に生まれてから今に至るすべての時代を憎み、すべての文化を憎んだか?お前は小学校を卒業するまでJ-Popを「世界に一つだけの花 」と「TSUNAMI 」しか知らなかった、しかも教科書か何かで知った。だがそれまでは地元大卒の両親の家にあったささやかな、しかしありがたい本棚、そして図書館にあったCDを聴いていただろう。そのせいではないがお前はRadiohead を長い間「amnesiac」しか知らずそればかり聴いていた。YouTube に出会ってからはBump of Chicken やEXILE やMr. Children やスキマスイッチ や椎名林檎 ・東京事変 の動画を観ていただろう。だがそれ以上に、随分昔に死んだ人間の音楽が好きだっただろう。「dig」なんて言葉は聞いたこともなく、発想することさえなかった。お前はとても広くて狭い世界に閉じていた。自分で何かをしようと思って何かをやった記憶がなかった。なんとなく出会って、気持ちよくなったことを延々とやっていただろう。怒りや憎悪ではなくて、気持ち良いことのほうが好きだったはずだ。確かに激しやすさと快楽主義的なところが結びついていないかと言われれば難しいかもしれない。「快楽」という言葉に必ずしもしっくりきていなかったことを思い出せたのは友人のPのおかげだな。「快楽」ばかりではなく、快くないものから自分が確かに得ていたどす黒い「快楽」のようなもののことまで含めて考えると、お前は快楽主義者というより他人に見られているということを自覚していない校庭のつむじ風、いやつむじ風は見られていることを自覚していないだろうから単に校庭のつむじ風のようなものだった。お前が「主義」という言葉の気持ち悪さに気づきつつも、その言葉をなかなか振り払えないことに悩み始めるのはそれから随分先のことだ。ただただエネルギーを持て余していて今なおくすぶり続けるお前は学校という制度を憎みすぎており、学校に愛着を持つような人間、リアルの学校でうまく行かなかったせいかは知らないがいい歳になってインターネット上で学校を繰り返そうとしている人間を憎みすぎているが、このような形でお前自身学校から逃れることができていない。どちらがどちらの原因なのか、どちらでもあるのか、それもわからないでいる。人間は自分の中にあるものしか憎むことができない。「気持ち悪い」とか「嫌い」とかとの違いはそこにある。憎む力の吸引力はとても強く、お前はいつも自分自身が憎んでいるものに似ていく。「読書人」を、「本好き」を、心の底から軽蔑するお前。「趣味」を排斥したがるお前。だがお前の現状はまったく「読書人」であり「本好き」でしかないこと、自分自身のやりようが「趣味」であることにお前自身気づいている。そんな自分のことを確かに愛している面さえある。お前はバラバラに壊れてしまっている。いつ壊れたかも思い出せないぐらい昔から。だがお前は確かに幸福な時間を作っていたことがあったんじゃないのか?けして一人でではない。人並みに「友人」という言葉に悩みながらも、確かに友人がいて、彼ら彼女らなしではありえなかった時間を作っていたことがあったんじゃないのか?お前は高校生以来再びクラシックを聴くようになり、高校の終わりくらいから関わるようになったジャズは今でも聴いている。多分この2つが最もエロティックな音楽だからだろう。歌詞がエロければエロい音楽になるなんてことはない。いっても前戯みたいな音楽が精一杯で、音楽自体が絶頂するようなところにはなかなかいかない。日本語の歌はあまり聞かないままで、なぜなら今でも音の意味と歌詞の意味を同時にうまく処理できなくて頭がおかしくなりそうになるからだが、そんなのは些末なことで今年もたくさんの素晴らしい音楽を聴いただろう。お前はエヴァン・パーカー の1978年の未発表ソロライブ音源を聴いて、「こんな小説が書きたい」と思った。
リリースが止まらないToiret Statusに脳を無限次元へとグリッドされた。
もう20歳になったジョーイ・アレキサンダー のインタープレイ の広がりは現在世界一だろうと思った。
前まではフィジカルも出していたが新譜をデジタルでしか出してないパターンを目撃し、その中から2枚をよく聴いた。Yusef KamaalからハマったKamaal Williamsの骨格が見えた気がした。
Stings
Kamaal Williams
ジャズ
¥2139
ビビッドネスが四方八方からやってきて最高だった。
ジャケットでいったが、「Nice」のシンコペーション で気持ちよくなりまくっていた。
そのGenevieve ArtadiとLouis Coleのユニット、KnowerがForeverにたどり着いていて、おれも家でごちゃごちゃするぞ、と思った。
タイショーン・ソーリーの確信に満ちた音色と構築が好きだった。
最初に出会ったときはニューオーリンズ ・ジャズのスタイルで若々しく心地よい音がしていたのが、今はTVショーがそのままアルバムになるようなメガポップなものまで聴かせてくれることになった。
久々にリーダーアルバムを出してくれただけで嬉しかった。こんなタッチで、意志を持った小雨のように始めてくれるピアニストはジェイソン・モランだけだと思った。
Refract
ジェイソン・モラン, マーカス・ギルモア & Blankfor.ms
ジャズ
¥2444
クリス・ポッターはやっぱり最高のテナー・サックスプレイヤーだった。
公式には2年前にはリリースされているはずなのに、レーベルがサンクトペテルブルク に位置しているためか知らんが、Amazon ではまだ予約受付中の新譜となっている最高のストレート・アヘッド・ジャズだった。お前はこいつをまともに買えるようになってほしいというだけでもさっさと戦争をやめろと今年も思い続けていた。
ド年末に新譜を出されて嬉しかった。まだ自分が好きになれる日本語のロックがあった。
小さくて優しげな場所、天気雨上がりの路地の匂いがしてよかった。
友人たちと話しながら、ポップスの条件として①適度に聞き流せるが、冷静に考えると何を言っているのかすぐにはよくわからない歌詞②口ずさみやすく、少しだけひねりを隠してあるメロディー③譜面全体の直感的な読みやすさ、があるだろうな、と思った一年だったが、瑛人は特に①で尋常ではなかった。大体「香水」の時点で、サビ5,6小節目という大事な部分を省略なしブランド名で埋める男が尋常であるわけがないのだった(香水のブランド名全然詳しくないけど「エルメス 」とか短くすればもっと歌詞が動かしやすくないか!?「ドルチェ・アンド・ガッバーナ 」て!)。新譜一曲目のタイトルに「チャリで歌うやつ」を選択できる瑛人はやはり尋常の人ではないのであり、正統に洗練を深めるOfficial 髭男dismと合わせたこの二者が今のJ-Popを背負っていると勝手に思っていた。
日本語歌曲の最高傑作を「赤とんぼ」と信じて疑わないお前。8小節×4回のリピートで十分に世界は現れるのに、今の歌はどれもこれも歌詞が長過ぎてとても聴いていられないそもそも詩じゃねえだろこれという風にこじれていったお前。「赤とんぼ」にシューマン の匂いを感じてはいたが(メロディーライン、3/4だがその拍子感が曲からは曖昧にしか感じられないことなど)、本当にシューマン にネタ元っぽいものがあると知ったのは今年、「序奏と協奏的アレグロ 」。お前は自分の「dig」性のなさを再認識し、自分がオタクではないこと、否オタクにはなれないことについて思ったりしていた。
ディエゴ・スキッシの、タンゴ編成の可変性と拡張性を突き詰める姿勢にやられた。
クラシックの新譜を聴いていいなと思うことはほぼないが、ヒラリー・ハーン のイザイは聴いて「この人こんなにいいヴァイオリニストだったっけ?!」と驚いて過去作から順繰りに聴いていた。結果、ヒラリー・ハーン はデビューしてからずっと良くなり続けていたんだと思った。10歳でカーティス音楽院入学。同じく10歳でそこへ進学したHIMARIのことを考えたりした。あんまり周りの期待のことは気にしないでのびのび生きていってくれたらなと思った。
アルベルト・ヒナステラ の良さに気づいた。バルトーク が好きならもっと昔にハマっても良かったはずだけれど、ふさわしい時というものがあった。アストル・ピアソラ の師匠だった時期があるというのを知るのに、ディエゴ・スキッシにドはまりする必要があったのだった。
生きている間にミクローシュ・ペレーニの演奏が聴きたい、と、リゲティ の無伴奏 を聴きながら噛み締めていた。
シマノフスキ の「神話」という、今までに聴いた音楽の中でもトップクラスにエロティックな曲、そしてクシシュトフ・ヤコヴィッチ という良いポーランド のヴァイオリニストを知ることができた。もしかしたら本当に凄いアーティストは地元を離れないせいで知られずにいたりするのではないかと友人のPと話したりした。
NEOSを知り、今もたしかにある現代音楽の響きを静かに追おうと思った。
ドイツ的なもの、というよりドイツ的精神そのもののように思える交響曲 というジャンルを終わらせたのは、「ドイツ人」ではなかった二人、シベリウス とマーラー だっただろうと思った。シベリウス はその核へと凝縮していく過程で交響曲 自体が削ぎ落とされていくという形で、マーラー は交響曲 が極限まで膨張していく過程に交響曲 自身が耐えられなくなっていくという形で(補筆された10番の2楽章以降はどれもこれもマーラー 自身の深化から退行していて聴いていられない)。ドイツ帝国 の終わりとともに、ドイツ的な精神、交響曲 という精神はロシアへと旅立ったが(プーチン がドイツの反動思想家たちの本を読んでいたというのは、何かお前を素直に納得させるものがあった)、そこからの交響曲 はどうしても交響曲 自身のパロディの影なしにはありえないという匂いがした。もちろんラフマニノフ のような人はいるにせよ。
お前は『セロトニン 』を読んだあとに今までの感謝をもってウエルベック に別れを告げてから、「現代フランスに存在する見るべき文化はレイシズム しかない」などと嘯いていたが(もちろんそれは昔フランスからの留学生に「今の日本にある面白い文化は緊縛だけ」と煽られたのにピキッときたからというのもあるけれど)、そうは言っても今年のお前はお前の大嫌いなフランス国家に感謝しなければいけないなと薄々感じていた。フランス国立図書館 (BnF )が持つ膨大な録音アーカイヴを商業利用へと広げるプロジェクト「BnF Collection sonore」、お前はサブスクで今年どれだけお世話になったかわからない。
今年いずみホール で聴いた「Golden Slumbers」の後半、永遠に続くんじゃないかと思われた和音の連打が、見ることの決してできない雲になっていた気がして、まだあの時間が頭の中で鳴っている。演奏終了後、疲労 が溜まったのかブラッド・メルドー が雫を払おうとするように両腕を振っていたのを思い出す。とても背の高い大きい人が低い椅子に座っていて、歳は取ったけれども、寡黙で聡明な永遠の少年がそのままそこにいるように思えた。
brad-mehldau-japan.srptokyo.com
際限がなくなってしまう。お前はそれくらい今の「文化」からたくさんのものをもらっている。十分すぎるぐらいそのことを知っている。それなのにお前は「文化」を憎み、その下支えをし、また「文化」によって変容もする「文明」を憎んでいる。気持ちは分からなくはない。お前がアドルノ から「反ナチのナチ」という匂いを感じながら、突き放す気になかなかなれないのも、「この世界の何もかも気に食わねえ」ということがそれ自体全体的な救済への渇望であることに気づいているからだろう。そしてお前はそれに気づいているがゆえに「救済」や「祈り」といった概念を唾棄したがるのだろう。
お前は今の文学がほとんど読めなくなったと言ったが、それはほとんど照れ隠しであって、でなければ何度も新刊ばかり置いてある本屋に行くわけがない。だいたい、お前自身が詩人追放論を対偶として読んだのだ。「文学」の静かな隆盛にお前が瘴気を感じているとしたなら、それは文学に携わる者たちが悪意を働かせているのではない、ましてや「文学」が文学を超えた瘴気の蔓延の十分条件 になっているわけではない。むしろ瘴気がお前自身を含め、世を覆い尽くしている、文学もまたその瘴気に飲まれているということであるはずだ。お前が付かず離れず意識を向けているハイデガー 、すべての肖像写真に邪悪さの影を引きずっている、思索する人。彼は好んでヘルダーリン の「危機のあるところ、救いもまた育つ」を引いたのではなかったか。これは論理的な啓示であろう。危機がないところではそもそも救いは必要とされないがゆえ、そこで救いは見捨てられているのだから。「求めよ、さらば与えられん」は、それを信じる者の想像を超えた広さにおいて正しい。ハイデガー の相貌に漂う邪悪さの理由は判然としないが、あのような思索へと向かうことを欲するもののなかに、「救いのために、危機を求める」という倒立したものがなかったかどうか。お前は自分自身のあらゆる神経を摩耗させながら同時に高揚してもいることに気づいている。お前は静穏と同じくらい動乱を求めている。それはお前が唾棄する「青春」の名で呼ばれているものではないのか。未熟そのもの。お前は大人と子どもの違いを考えたとき、「趣味」の有無というところにたどり着いたはずだ。大人には趣味があるが、子どもにはない。子どもは「趣味」で遊んだりしない。子どもは生きることの全体に対して真剣なのだ。現状それはもちろん、子どもが労働世界の陰鬱な掟から切り離されているから可能なことであり、労働世界に投げ入れられる人間は生の全体性を24時間という与件によって労働時間と余暇時間に分割される。世俗的な語用としての「大人」は、労働世界との直面によって分裂した生を前提している。お前がすべての時間を労働へ投入する労働エリートに対して尊敬と畏怖の念を抱くのも無理からぬことだ。すでに基体としての生が砕け散っているにも関わらず、余暇時間の現象でしかない「趣味」を生きがいとすることは、この条件下で「生きがい」なるものによってまるで生の統一が可能であるかのような欺瞞を生むだけでしかない、そうお前は考えた。断片、お前の断片はお前の過去を高速で蘇らせる。そこには言行の根拠になることは何一つないが、ただ蘇ったことだけは証されている。お前はお前であるもののすべてであり、粉々になったお前を継ぎ合わせたもの以上のものだ。お前はそのことにどこかで気づいていたから、今年を今年だけで振り返ることができなくなってしまったのではなかったのか。そして今、お前は「趣味」を憎悪によって根絶しようとしている。が、それはお前が信じるお前のプラトン を裏切っている。生の分解を引き起こしたのは趣味ではない。この世界、大人が作った世界、戦争と略奪と憎悪と差別と冷笑と生贄とその他諸々を構造的に組み込むことなしには成立しない世界が存在する限り、生は分裂させられる。子どもはどんどん大人びはじめる、そう強いられる。この基底がひっくり返らない限り、この腐った土壌から生えてくる「希望」なるものはすべて麻薬でしかない、いかにして子どもでありつづけられるか、それくらいしか、今生、自分が取り組み得ることはない、という風にもかつてお前は考えていたはずだ。しかし、この一年で出会った大人たちはみな万死に値するクズどもばかりだったか?そんなはずはない。お前は確かに助けられ続けた。いい大人たちがいて、子どもたちがいて、ここはたしかにお前のような人間だからこそ信じるべき世界だと思えた瞬間があったのではなかったか?お前を駆り立てる反知性「主義」は、お前が目の前を見失わないためにこそお前が求めたものだったのではないか?そして、もしお前が目の前を見失わずにいられるのなら、その反知性「主義」は必ずしもお前にとってなくてはならないものではないのではないか。お前がお前の嫌う「本好き」でしかなかったとしても、人のつながりの助けもあってこの一年でお前は色々な素晴らしい本に出会った。根っこまで参ってしまいほとんど文字が読めなくなってしまっても、きっと荒木時彦の詩集は読めるだろうと思った。
幽体離脱 で離脱するのは二元論的な「精神」ではないことを確信し、身体をもって生まれたことに感謝した。
高橋源一郎 に出会って、「ゴースト」や「悪」と戦うためには、「『敵』と戦う」のようでは全然ダメなんだと確信した。
非常に大雑把に言って、ハイデガー のように詩へ向かうものと、ヴィトゲンシュタイン のように詩へ向かうもの、2つの詩をめぐる本の間を反復横とびしながら、ここ2年くらいで急速に現代詩にハマっていった歩みを思い出していた。
ハイデガー との会い方を陰に陽に教えてくれるありがたい本だと思った。会い方というのは姿勢や挨拶のことだ。
「納得できない」ということに対して全力で向き合うために、ほとんど書き方を一から考え直さなければいけないというところまで自分を持っていく、藤井貞和 という真剣の人のことを知った。(『釈迢空 』を読んだあたりからお前は「批評文」のような批評文への関心を喪失し、元々ろくに書けてはいなかったわけだが書くことからも読むことからも遠ざかっていた。それはもちろん藤井貞和 のせいではなく、お前の気持ちが素直じゃなかったせいだ。それに気づいたのか、最近は少しずつリハビリをしようとしている。あと一つだけ。捨てるべき記憶などないし、そんなことはできない。忘れないでいてほしい。)
本当に凄まじい思考というのは、こちらに「議論」をしたいという気持ちを起こさせるものではなく、「ああ、もうこうとしか考えられない、こうだな」という気持ちで満たすのだと思った。「腹に落ちる」というのはとても物理的な現象である気がした。もちろんそのように書いてあるのだが。
お前はあれだけ現代短歌を拒絶していたが、全面的にそうというわけではなかった。この、風が木になって立っているような歌集のことを、多分この一年間だけでなく、これから先も灯火にするだろうと思った。
お前が「加害/被害」と「自由/運命」のように考えるようになったのは、この本に出会ったからだろうと思い返していた。
「おおよそ現代の日本語話者全体に絶望してしまうような気分」のときにこの2冊を読み、かつてこのように立派な佇まいの人たちがいたのだと思い、比喩でなく涙が出たことがあった。そして涙を出しながらも、自分は「政治的」な刺激に対する情感の閾値 が極めて低く、おそらく映画版「永遠の0」を観たら泣いてしまうのだろうなとも思った。小説版『永遠の0』を読んでいたときは全く泣くことはなかったが、そんなことよりも小説が全編にわたって教養バラエティ番組の文法で書かれていることに衝撃を受け、これが大ベストセラーになったということの意味を考え込んでしまったことも思い出した。
大風呂敷を広げられるだけで嬉しくなれるものだなと思った。
とてもカラッとしていて、涙を流さないで良いというのは気持ちがいいことだと思った。
「恐ろしい面白さ」という概念が存在することを教えてくれる本だと思った。
今年も現代詩文庫を読んでいた。特に山本道子は、最後の最後に収録された詩「どこへ行ってしまうの」が衝撃的で(
YouTube には山本の友人である吉
原幸子 による朗読がある。
放送禁止用語 のある行含め三行が省略されているが)、しばらく小説も追っていた。描写を見るに霊感があるとしか思えないのだが、そういった世界との距離感が独特であり、それ以外のところでもあまり見られない妙な迫力があるのでハマってしまう。今どうしておられるのだろうか。とお前は思った。
VIDEO youtu.be
ひとりではあるのだが、ひとりではないと思った。
お前は今まで自分の作ったものを見返すということをほぼしなかった。お前が言葉を書く理由は、忘れるため、頭の中にひたすら沈殿していく澱の重みから逃れるため、頭を軽くするため。だからお前にとって読み返すことはおかしなことだった。だがお前は同時に思い出すようである書くことへ向かっている。「ひとは自分が知っていたことしか知ることができない」、「ひとは自分に与えられたものしかだれかに与えることができない」という命題を今年何度思い出した?何か進展はあったか?ちっとも進まなかったか?この残酷かつ温かい直感をお前は抱き続ける、これはもう思い出すことではない、お前は記憶と現在の区別がほとんどつけられないようなところで生きはじめている。無理に自分の過去を振り返れと言っているのではない。そんなことを言わなくても記憶の方から自分のところへやってくることをお前は知っている。それを悪霊のように振り払う、遠くへやろうとするお前。それ以外に、本当に道はないのか?「サッチャー ・バイブス」すなわちThere is no alternative .がお前を突き動かしてきた一年だったかもしれない。たしかにそれがなければお前はこの一年戦えなかったかもしれない。いや、もっと正確にしよう。お前は「ここではないここ」を目指していたのではないのか。そこでいまどこにいるかは聞かないでおこう。最後に一つだけお前に思い出してほしい。「多様性」の入った文章にもことごとくお前は邪悪を感じたと書いていたが、お前がAmazonプライム でかつて観た、今は観ることのできない、カマシ ・ワシントンの「ライブ・アット・ザ・アポロ・シアター 」。そこでの正確な翻訳をお前は忘れた。インターネットに出てくる記事を見て、そこに引用されている文章を確認したがしっくりこなかった。お前は2020年に公開されたこのコンサート映像の中でカマシ ・ワシントンが「多様性」について語った言葉をこう記憶している。
多様性とは許容されるものではなく、祝福されるものだ。
https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B084CXXRSP/ref=atv_dp_share_cu_r
おそらく視聴してから3年経ったあとも、お前はこの言葉に黒魔術の影がないことを確信する。そして「祝福される」というフレーズにおののく。「祝福する」でも「祝福すべき」でもない。限界まで「神」という概念には頼らないで踏ん張って考えるということを柱としてやってきたお前に、この言葉遣いがどれだけ深く突き刺さったか。しかしカマシ ・ワシントンも「神」とは多分言っていなかった、そのことが「祝福される」、受動態のパワーを際立たせている。祝福される。お前はまだこのような言葉を発することができる人間、そう、それはやはり文章を書くことを本職にしている人間の言葉ではなかった。それは確かにお前を沈ませたが、しかしそれでもこのような言葉を発することのできる人間がまだこの地上に存在するのは確かなことなのだ。「人間は自分が何を言っているのか分からない」とお前はここ一年でますます強く思ってきた。もし自分が何を言っているのかが自分で全部わかるのだとしたら、多分言葉を実際に口にする必要はなく、ひとり頭の中でどんどん展開させていけばいい。会話なんて生まれなかったんじゃないだろうか。このことは多分さびしさと繋がっている。他人の恋バナは他人事のように聞けるのに、自分の恋となるとまったく他人事のようにできないのに似ている。……いいのかこんなことで?やっぱりお前は頭がおかしくなったんじゃないか?とも思ってしまう。
「俺以外全員おかしくなってしまった」と「俺がおかしくなってしまった」という相反する方向へ力が加わり、支柱となる俺の背骨はコマのように回転しているわけだが、冷静に考えればここはこだわるべきところでもないのだった。大穴で「俺含め全員おかしくなってしまった」というパターンもあるがもういい。おかしくなってしまったらおかしくなってしまったで、その後どうなるかもはっきりとわからないまま、だが何もできないわけでもないまま俺たちは続いていくのだから。天竜 川ナコン、ありがとうな。
VIDEO youtu.be
VIDEO youtu.be
その他、今年発したフレーズ
・「日本の可能性の中心、愛知県立旭丘高等学校 」
→葉ね文庫などで発した。歴代卒業生には荒川修作 だけでなく、赤瀬川原平 、祖父江慎 、岡井隆 といった、ラディカルな仕事、デカいバイブスで仕事をしていた人々が多数在籍していた。更に名古屋藩立「洋学校」であった時代までを含めると、坪内逍遥 と二葉亭四迷 がここ出身であり、少なくとも「教科書的」な日本近代小説史はこの学校を卒業した二人から始まっている。なんというラディカル。いったい愛知県立旭丘高等学校 にはどんなエネルギーが潜んでいるのか、一切が不明となっている。
・「ボルヘス を引きはじめるのは衰弱の証」
→葉ね文庫などで発した。こいつ葉ね文庫などでしか発しないのか。個人的にはボルヘス はたまに読む分には楽しく読める作家、あんまりいい奴そうには思えないけど……という感じで嫌いというわけではない。なんでこんな風に思うようになったんだろうというのがあんまりよくわかんないのだが、ボルヘス の作品って、世界で一番デカい子供部屋の中で、おもちゃ同士を組み合わせた新しい遊びを次から次へ見せてくれる……といった向きで、楽しいんだけど、外に出たいってモチベーションには合わねえんだよな(レムやコルタサル はこのへんボルヘス と読感が違う)、というのがありそうである。ところで村上春樹 の新刊が平積みにされていた頃、「あとがき」を真っ先に読んでそこに「ボルヘス 」の文字を確認したとき、「了解!!!!」と思った。
・「◯月、無理ゲーをやらせていただいているという感謝の気持ちが大事な季節」
→主にTwitter で各月初に発した。はじめはわりかしユーモアのつもりで言っていたわけだが、だんだんマジ要素があるんじゃないかという考えに変わっていった。しかしこういうものをあまりにマジに受け止めすぎると人間はたいていブっ壊れるため、俺はふざけているという感覚もまた大事にしていきたい。
さいごに
今年の目標は「単著作る」と「引っ越し」であり、達成度は50%となった。詩集『やーばん』を作りました。
手元にあと4冊しかありませんが、大阪市北区 は中崎町 にあります『葉ね文庫』さん、『深夜喫茶マンサルド』さんでも取り扱って頂いております。ぜひ足をお運びください。
それでは、また、皆様、良いお年を。本当に。






























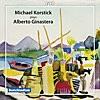















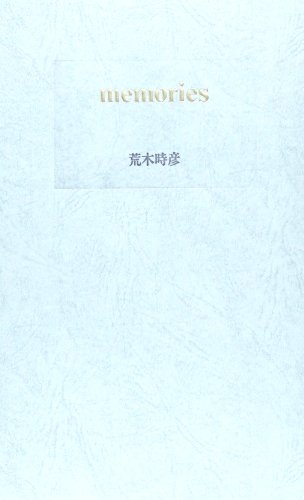























![まっぷたつの子爵[新訳] (白水Uブックス) まっぷたつの子爵[新訳] (白水Uブックス)](https://m.media-amazon.com/images/I/51iaMtyQWoL._SL500_.jpg)



