「きみもクリエイター(クソみたいな語彙)になれる!クリエイター(クソみたいな語彙)になろう!」式に資本から発せられるメッセージは、同志同士の競争過程へと人間を駆り立て、果てしない消耗の中から浮いてくるアガリをはねることを目標に放たれているわけで、こう聞くとクリエイティヴ(クソみたいな語彙)な活動をするというのはつらく、くるしく、自身を際限無く衰弱させる愚劣な行為、今すぐやめたほうがいいみたいな感じになるがそれはイデオロギー(イデオロギー、と読みます)のせいと考えることができる。すなわち、この前提には創造性という概念が「何らかの美的*1な稀少性に拠って交換価値を持つ商品を創造する能力」と同一のものとして考えられており、例えばあなたが自室のトイレで大便を排泄した際、排泄した大便を流す前に、誰に見せるともなくそれを素手で加工し、瞬間的にしか存在しないさせる気もない塑像を毎回のように作っているとしても、それは以上の記述から全く商品価値を持たないため、創造性とはみなされないとされるのだ。あなたはこの私秘的大便塑造行為をやり終わったあとちゃんと手を洗っているか? ならいい。存分に励んでほしい。
ともあれこのような状況下でもなおクリエイティヴ(クソみたいな語彙)な仕事で飯を食いたいという新参者が消滅しそうな気配は一向になく(というか私もクリエイティヴ((クソみたいな語彙))な仕事で飯を食いたいと思っている人間の一人であるが)、一切が謎めいている、というわけではないがそれはそれとして、クリエイティヴ(クソみたいな語彙)な仕事の他に、政治活動という分野がある。政治活動は一般にクリエイティヴ(クソみたいな語彙)な行為とみなされてはいない*2。それは「なんかあれ嫌すぎる、なんとかならんか、せなあかんやろ、せいや!」や、「こうしたらいいだろ、なんとかならんか、せなあかんやろ、せいや!」や、前述二文の末尾「せいや!」→「するぞ!」の変換によって得られる各種意識によって発生したり、なんとなくデモやっているからついていくか、なんか投票日だった、紙に特定の人名を書き、箱に投入するか、などといったバリエーションがあるがとにかくクリエイティヴ(クソみたいな語彙)な活動との大きな違いは、原則的に同志同士の競争過程という形を取らないところだ。「より強えーやつがカッケエ」みたいな話ではなく、とりあえず何らかの政治目標があったとして、それが実現したとすればそれに最も貢献したのは誰か、とかそいつは経済的に報われるべきだ、みたいなことはひとまず重要ではないということが言いたかった。今は「今からクリエイティヴ(クソみたいな語彙)な活動や政治活動をしようかな」という段階の人間の視点で話をしているんだ。制度論やら戦術論やら内ゲバの歴史やらの話はしていない。とにかく同志同士で消耗することなく何かを実現しようとする動き、少なくとも理想的には政治活動をそのように言っていい。いいだろ、言わせてくれ、頼みます。
さてこうなってくるとなぜわざわざつらく、くるしく、自身を際限無く衰弱させる愚劣な行為(イデオロギー((イデオロギー、と読みます)))ことクリエイティヴ(クソみたいな語彙)な活動を止めて、政治活動に邁進しないのか不思議でしょうがなくなってくるように見えるが、見えるのは一瞬だけで、当然いくつか言いたいことが出てくる。①どっちもやればよくね?②やっぱ違いはデカくね?
①労働経済学から学べる画期的な知見として「一日には二十四時間ある」ということと、「経済主体には働いている時間と、働いていない時間がある」というものがあり、こういう風に書くとあんまりにもあんまりだがそう馬鹿にするものでもなくて、両立しようとするならクリエイティヴ(クソみたいな語彙)な活動と、それで食って行けなければ賃労働の時間と、政治活動の時間を平等に所与としてある24時間のうちで割り振らなければならない。だが厳しいことに、クリエイティヴ(クソみたいな語彙)な領域にある行為は、先述のイデオロギーと一体化している場合、あらゆる仕事の中でもトップレベルに位置する過酷な資本の投入を要求する。そら詩とかパンクスをすぐに反例に上げたくなる気持ちはわかるが、パンクスはそのジャンルの歴史的コンテクストに乗れるかがめちゃ大事で詩はそもそも売れてねえだろ! 創造行為の話じゃなくて「クリエイティヴ(クソみたいな語彙)な仕事」の話に専念させてくれというわけで話を戻すと、美的価値に基づく商品ジャンルは(特に現在)猛烈な速度で洗練していくが、個々の商品の洗練の度合いは、大体、生まれてきてからその商品を生み出すまでにクリエイターが関係領域に投入した時間と資本の量に比例する(映画の話をやめろ!)。「天才」という文字からは甘いにおいがしますね。しますか? 天才というのはそのように表示された文字で、それだけです。突き抜けたいなら他のことやってる場合ではない。この領域に新規参入するにあたり週5・8時間労働などというのは舐めきっており(例えば『天才による凡人のための短歌教室』を参照)、世間には夢の中で書いた文章を起床後現実に持ってこれる小説家まで存在するという。恐ろしい話であり生身の人間による365日24時間労働の可能性が示唆されたわけだが普通に寝たほうがいいという話もあり実践にあたっては諸説あるが諸説あるとかいい出したらここで投入される資本には具体的な活動ジャンルにもよるけど「ボーッとする」とか「遊びまくるとか」とか言ってしまえば「政治活動をしてみる」とかだって選択肢になりそうになってくると話が全部おじゃんになってしまう! どうしよう! 今のはなかったことにしてくれ! また脇道にそれてしまったので戻すと、クリエイティヴ(クソみたいな語彙)な行為を仕事にできるほど突き抜けられた人間は「競争社会の権化」みたいなことになってくる。マジ成功したいのに政治活動などやっている場合なのか? となるのももっともなことである(もうある程度突き抜けて時間や資本に余裕のあるやつの話はしていない、「今から〜しようかな」の人間の話だとさっきいった)。これらの話をぜんぶドブに捨てる例外があるが後述する。
②デカい。政治運動をするのと、評伝『大便師・大海軽暗』を執筆することの間にはやはり差がある*3。どこかで欲望というものがあって(パラメータ的な話だけど)、芸術やらエンタメやらなんやらに行く方向と、政治活動やらボランティアやらに行く方向と、人それぞれ偏りがあるように見える。やはりこの二つを両立させるのは難しいのか。しかし、差がなくなる場所というものが存在する。
要するに、政治活動とクリエイティヴ(クソみたいな語彙)な仕事を完全に同一化するという選択肢があり、いわゆるファシズム(政治の美学化)であって、文字通り現実世界を制作するというアートに人生をぶっこむということは考えうる。大変困ったことであり、これに対してネチネチと(それこそクリエイティヴ((クソみたいな語彙))のように)反論を考えてもいいのだが、しない。ここでは、「お前のやってることが『世界を作り出すこと』っつったってその世界はフィクションでしょ。こっちの政治はノンフィクションな世界を作り出すアートなわけ。お前、ショボない?」と言われるシチュエーションに集中したほうがいい気がする。「アートとしてのファシズムが現実化しうる、考えうる限りで最も美的に魅力的な世界」に対して拮抗しうる「フィクショナルな世界」とはそもそもどういうことなのか、何が起きているのか、ここへきて確かに一切が急速に判明ではなくなってくるが*4、私は欲張りだからフィクションもノンフィクションも諦めたくはない。しかしこんなにガチガチな感じでやる必要があったんだろうか。自室のトイレで大便を排泄した際、排泄した大便を流す前に、誰に見せるともなくそれを素手で加工し、瞬間的にしか存在しないさせる気もない塑像を毎回のように作っているあなたのことを考えると、もう少し肩の力を抜いてやっていってもいい気がしている。
団鬼六先生、本当に申し訳ありませんでした。
本文中ではどスパルタみたいに見える書き方になってしまったが(とはいってもある程度いくとどスパルタ性も見えてくるのだが)、今から短歌を始めようとしている人への優しさが第一に伝わってくる。いい本だと思う。
「現実制作としてのアート=政治」を考える時、いつもここに立ち返ってくる。世界制作者=世界征服者としてのスターリン。この記事を書いていて、ボリス・グロイスは今でも自分が追っている数少ない批評家だということに気づいた。
*1:理想としての真善美というのはまだなんとなく受け入れられるものの、現実を分析するに当たっての対概念を考える時、真/偽、善/悪はまだいいとして、美の対概念となるとどうしてもモヤモヤしてしまう。境界を超えるにしてもそれには当然境界が前提されなければならないので、例えば美/醜と入れてみるが、これではあまりにもカバーされていないものが多すぎるし、しかしカバーされていないものをどの対概念でカバーしようかとなると、やはり美/?という感じがしてしまう。美という理念はどうも、真や善に比べてあまりに多大なものを背負わされている感がしなくもない。ともあれここでの美的はとりあえず美/非美とでもいうほかない二項を前提としているとおおらかに受け取ってほしい。ここを詰めはじめたら全然別の記事になっちゃうだろ。現在では美と、美の対概念になりそうなものとの境界がことごとく溶解しているように思われる。
*2:「政治とは可能性のアートである」という言葉があるが、それを踏まえれば「クリエイティヴ(クソみたいな語彙)な仕事とは可能性から/へのアートである」という形でひとまず差異を表現することができるかもしれない、が、本文にはうまく繋がらないなあということで以降本文が蛇足のように存在するわけである。というより書き終わってみると本文全体が蛇足だろというか全く凡庸なことしか言っていないな〜という気持ちになってすっきりした。
本文に書いていることの大半は昨日寝る前にぼんやりと考えていたことであるが、どうしてこんなことを考えたのだろうと考えてみると、クリエイターに分類されるであろう多くの仕事は、(実質的に)フリーランスの個人が、巨大な生産技術と流通技術を持つ資本と協働することによってなされている。フリーランスという語は傭兵の謂であって、近年(マネタイズがいくらかでも可能になるようなインターネット各種インフラが整備されたのはデカい)なにかクリエイティヴなことをやろうという人間が増えているということはつまり傭兵志望者が増えているということか! 潜在的に増え続けている在野の兵士たち……おもしろ! ということはどういうことがいえるだろう……とイメージが短絡した結果だなあと思い至った。
とはいえ特に結論部に関してはムヤムヤと折りに触れ思い出される問題だったし、書いてみて、そうか、そのように自分は思っていたのだな、と気づいたところがある。書かなくても考えることはできるが、書くと手をかける場所のようなものができるのを感じる。頭の中は見えないが文字は見えるということはとても大きいことなのだろう。大きいことといえば、自室のトイレで大便を排泄した際、排泄した大便を流す前に、誰に見せるともなくそれを素手で加工し、瞬間的にしか存在しないさせる気もない塑像を毎回のように作っている人間が一人もいない世界がこの世界だとしたら、どうだろう。それでいいと100%思いながら超過した5%くらいで「ちょっと寂しい……」と思うのではないだろうか。私はあなたに、自室のトイレで大便を排泄した際、排泄した大便を流す前に、誰に見せるともなくそれを素手で加工し、瞬間的にしか存在しないさせる気もない塑像を毎回のように作っている人間になって欲しいとは、全く、決して、100%思っていないし、無論超過した5%くらいでなって欲しいと思っているが、こうした秘めやかで過剰な欲求がかの大便師・大海軽暗を生み出したと言ってもいい。大海は「新宿の痔ならし屋」の異名を持つ、日本最強の大便師だった。大便師という言葉を聞いたことがなくても不思議ではない。かつて日本には「賭け排便」という博打があった。博打と言ってもなんのことはない。一本糞、この長さですべてが決まる。この一本糞をひり出す役目を負った者が「大便師」と呼ばれた。大きな勝負で他の大便師より短い糞を出してしまった大便師は、尻を拭く間もないまま命を奪われる危険さえある。そんな中、大海は勝ち続けた。圧倒的と言ってよかった。「一本勝負」とはちがい、「連チャン」ではただ長くひり出せばいいというものではない。予備糞を丁寧にコントロールし、今日の大一番がどこにあたるか、相手はどう考えているか、腸の調子はどうか、これらすべてを全身で読まなければならない。大海は「連チャン」でも負けなしだった。目にレントゲンがついていると言われた。相手の腸内が見えているかのように、絶妙な塩梅の一本糞をひり出し続けた。
生前、「どうしてあなたは勝ち続けられるのか」という、それまでなんども浴びただろう質問に、寡黙だった彼がただ一度だけ答えたことがある。彼ははにかみ、洗ったばかりの左手でボサボサの頭をかきながら、こう言った。
「固くなっちゃあダメだね。こっちがガチガチじゃあ、ウンコの機嫌が悪くなる」
*3:「書くことそのものが政治的なのだ」と、後ろめたいものなしに言い切ることが可能な状態というのは、その時々の政治的状況との関わり合い抜きには考えられない。「言うだけならタダ」という粗暴な言い回しがあるが、少なくとも書くということについて考えるに当たっては、この粗暴さをもっとも残酷な水準で受け止める気持ちはどこかで持っておいたほうがいいと思う。
*4:似た類型の話として、「理想世界においてフィクションは制作されるか?」というものがある。これに対してはプラトンの「詩人追放論」を経由して考えたことがある。理想国家というものがあって、詩人は現に追放されたのだと考えてみる。詩人がその詩により風紀を乱すから理想国家が実現されないという類の、詩人を原因とみなす考え方より、詩人が存在するのでここは理想国家ではない、と逆向きに考えるほうが私にはしっくりくる。信号としての詩人。私は人間の創造欲求というものを純粋な良きものとはとても考えられない。それは途方もなくややこしく、困ったもんですなあとなる類のものだろうという直感を今でもずっと抱いている。




![アバド / マーラー : 交響曲第2番 [DVD] アバド / マーラー : 交響曲第2番 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61IxlZy-2cL._SL500_.jpg)
![東京2020オリンピック SIDE:A/SIDE:B [Blu-ray] 東京2020オリンピック SIDE:A/SIDE:B [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61RX7d+x4yL._SL500_.jpg)


![PIANO SOLO [12 inch Analog] PIANO SOLO [12 inch Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/415VFUVtOQL._SL500_.jpg)





![Quality Over Opinion [輸入アナログ盤 / DLコード / ブラックヴァイナル仕様 / 2LP] (BF129)_1628 [Analog] Quality Over Opinion [輸入アナログ盤 / DLコード / ブラックヴァイナル仕様 / 2LP] (BF129)_1628 [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/31xCs+ZdQUL._SL500_.jpg)
![Blind [輸入アナログ盤 / DLコード / 1LP] (BF111)_1506 [Analog] Blind [輸入アナログ盤 / DLコード / 1LP] (BF111)_1506 [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/41ILtl+gukL._SL500_.jpg)













![空襲と文学[新装版] 空襲と文学[新装版]](https://m.media-amazon.com/images/I/41gP-+1OVXL._SL500_.jpg)



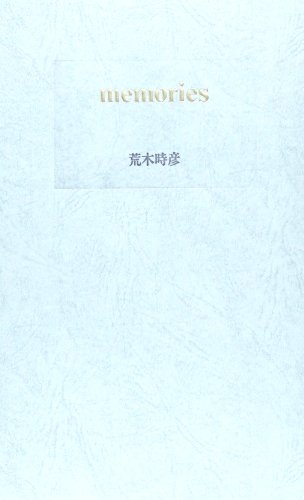

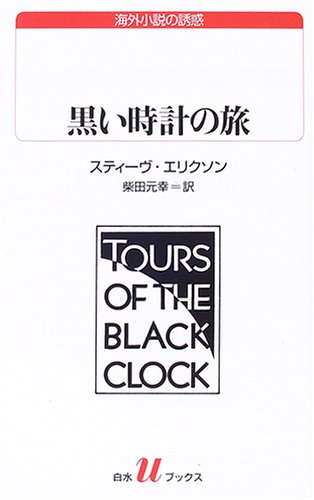












![【新ジャンル/第3のビール】本麒麟[500ml×24本] 【新ジャンル/第3のビール】本麒麟[500ml×24本]](https://m.media-amazon.com/images/I/51CREXm52zS._SL500_.jpg)



